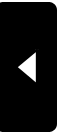紀州釣りの正しいタナ設定
紀州釣りで最も重要で難しいのがタナ取りです。
ところが、このタナ取りをおろそかにしている人がとても多いです。
最もよいタナとそうでないタナとでは、一日釣りをしていると釣果に大きな差が出てしまいます。

紀州釣りでチヌを狙う場合、基本的にはサシエが海底を這うようなイメージで仕掛けを流します。
なのでサシエが海底から浮き上らないようなタナ設定にしないと、なかなかチヌは釣れません。
とは言っても、海では干満の差によって水深が変わりますので、それに合わせて何度も調整しないとタナがうまく合いません。
また、潮の流れが早くなると仕掛けが斜めになり、タナをきっちり合わせたつもりでもサシエが海底から浮き上がってしまいます。
こんな時は仕掛けが斜めになった分ウキ下を長く取り、仕掛けをハワセ気味にしてサシエが浮き上がるのを防止しないとエサ取りばかり釣れてしまいます。
海底にはいないはずの魚(アジなど)が釣れた時はタナが合っていない証拠なので、こんな時はウキ下をさらに長くします。
紀州釣りの基本的なタナは底スレスレでサシエが浮き上がらないように注意することですが、状況に合わせてタナを変えてみることも釣果アップにつながります。
紀州釣りのタナは、底を少し切ったもの、底スレスレのいわゆるトントン、ハリスを海底にはわせたハワセがあります。
最近ではではハワセをする人がほとんどですが、ハワセなくてもタナさえ合っていればチヌは釣れます。
■底を切る
紀州釣りでチヌを狙って底を切る人はほとんどいないと思いますが、グレを狙う場合は底を切るのが一般的です。
少し底を切ってみると、ダンゴが割れた瞬間がとても分かりやすく、ダンゴ投入のテンポが良くなります。
グレを狙う場合は大きく底を切ることが多いですが、
たとえばグレ狙いで底を1~2ヒロほど切っていてもチヌが食い付くことがあります。
チヌが中層に浮いているような状況では、中層でダンゴを切ってサシエを落とし込んでみるのも面白いです。
アタリは道糸がスーッと走ったり、逆に止まったりするので、ウキ止めや道糸の動きでアタリを取ります。
チヌが中層に浮いている状況というのは普段でもよく見かけます。
たとえば夏場の高水温で海底が酸欠になっている時や、海が荒れて濁りが入っている状況なども中層は狙い目です。
また、水深のある釣場では、中層で釣れるチヌは型が良く、年無しクラスの大物も狙えます。
「紀州釣りは底をハワセないとチヌが釣れない」と思っている人がほとんどですが、そういう考えしか持っていない人には、「底を切ってチヌを釣る」というのがちょっと信じられないかもしれません。
また、岩場など底が粗い釣場では根がかり対策として少し底を切ります。
根がかり対策として底を切る場合、ダンゴは海底に届く直前に割れるように握り加減を調整します。
慣れるまではかなり難しいと思いますが、回数を重ねることで少しづつ握り加減やダンゴの水加減などが分かってきます。
■トントン
紀州釣りはダンゴの煙幕で海底にチヌを集めて釣りますが、トントンというのは紀州釣りでは最も基本的なタナ設定です。
ただ、トントンと言っても、実際には仕掛けが斜めになることがほとんどで、ウキ下は水深よりも少し長く取ることになります。
潮流や風の影響などで仕掛けが張って、ウキにダンゴのテンションがかかった状態を『トントン』と呼んでいます。
釣り始めは状況を見るためにトントンのタナに設定します。
トントンのメリットは、ダンゴが割れたタイミングが分かりやすく、魚のアタリが明確に出ることです。
エサ取りのアタリが明確に出ることで、空バリの状態で仕掛けを流すことも少なくなります。
また、タナをトントンにすることで、ハワセに比べ手返しが格段に早くなります。
チヌの活性が高い時は、サシエが少々浮いていてもバンバン食ってきますので、数釣りではトントンが有利です。
アタリが明確なので、チヌの硬い口に「掛け合わせる」事も可能になります。
■ハワセ釣り
ハワセ釣りとは、サシエを底に這わせたまま浮き上がらないように仕掛けを流すことです。
エサ取りが多い時、チヌの食いが渋い時などに多用します。
砂地以外では根掛かりが頻発しますので、波止や磯では海底が砂地のところまでダンゴを投げます。
ハワセ釣りの主な目的は2つです。
1、エサ取りが多い時、エサ取りにサシエが見つからないようにするためです。
基本的に落ちているエサというのは、エサ取りに強いです。エサ取りの大半は、海底より少し上にいるからです。
2、チヌの食いが渋い時、食い込みを良くするためです。
サシエを底に這わせることで、活性の低いチヌでも違和感なくサシエを食うため、食い込みが格段に良くなるというメリットがあります。
ハワセ釣りの釣り方ですが、基本的にハワセ釣りでは、どんな状況でもウキが常に海面より出でいる状態が正しいタナになります。
ダンゴの投入後ウキが海中に沈むようならウキ下を長くします。
ハワセと言うのは『ハリスを海底に這わせる』ということなのですが、実際にはハリスが全て海底に這っているという意味ではありません。
潮流や風などによって仕掛けが斜めになり、サシエサが浮き上ってしまうため、その分ウキ下を長めに取っておく、ということです。
ベタ凪の時では20cm程度のハワセで十分ですが、風や流れが強い時は1~2ヒロ、場合によっては3ヒロ以上もハワセる事もあります。
ハワセのメリットは、チヌの食い込みが良いのと、トントンの時ほどタナを気にしなくても、サシエの浮き上りを抑えられるという点です。
しかしあまり多くハワセすぎると、その分アタリが出にくくなります。
アタリが出にくいという事は、エサ取りのアタリも分からず、エサを取られたまま仕掛けをいつまでも流すことにもなります。
また、仕掛けを回収しようとリールを巻いたら勝手にチヌが釣れていた、という事にでもなると少し格好が悪いです。
実際にそういった経験をした人は多いですが、ハワセ過ぎが原因です。
できるだけチヌのアタリが分かる範囲でハワセるようにします。
基本的にハワセの場合、チヌがサシエを食って移動した時にウキにアタリが出ますので、居食いの時はアタリが出にくくなります。
もしアタリもなく勝手にチヌが釣れていた場合は、仕方がないので『違和感なく食わせたぞ!!』
とか言って、逆に自慢することです(笑)
まぁ、ハワセ釣りというのは元々それが狙いなので、間違ってはないです。
◎どれくらいのタナ設定が最適なのか?
たとえばハワセと言っても、どの程度はわせるのが良いのか、また、底を切る場合はどの程度なのか、トントンと言っても本当にサシエサが底まで届いているのかなど、正しいタナに設定することはとても難しいものです。
紀州釣りの正しいタナはその時々の条件で異なりますが、多くの経験を積むことで少しずつ解ってきます。
正しいタナとはチヌの食いが良く、はっきりとアタリが出るタナです。
潮流や風など、サシエサや仕掛けを浮き上らせたり、潮の干満によってタナを狂わせる要因があります。
しかし、どんな条件でも、常に正しいタナで紀州釣りをする事が釣果につながります。
これは言葉で習うより、まず実践して理解する事が大切かもしれません。
ところが、このタナ取りをおろそかにしている人がとても多いです。
最もよいタナとそうでないタナとでは、一日釣りをしていると釣果に大きな差が出てしまいます。

紀州釣りでチヌを狙う場合、基本的にはサシエが海底を這うようなイメージで仕掛けを流します。
なのでサシエが海底から浮き上らないようなタナ設定にしないと、なかなかチヌは釣れません。
とは言っても、海では干満の差によって水深が変わりますので、それに合わせて何度も調整しないとタナがうまく合いません。
また、潮の流れが早くなると仕掛けが斜めになり、タナをきっちり合わせたつもりでもサシエが海底から浮き上がってしまいます。
こんな時は仕掛けが斜めになった分ウキ下を長く取り、仕掛けをハワセ気味にしてサシエが浮き上がるのを防止しないとエサ取りばかり釣れてしまいます。
海底にはいないはずの魚(アジなど)が釣れた時はタナが合っていない証拠なので、こんな時はウキ下をさらに長くします。
紀州釣りの基本的なタナは底スレスレでサシエが浮き上がらないように注意することですが、状況に合わせてタナを変えてみることも釣果アップにつながります。
紀州釣りのタナは、底を少し切ったもの、底スレスレのいわゆるトントン、ハリスを海底にはわせたハワセがあります。
最近ではではハワセをする人がほとんどですが、ハワセなくてもタナさえ合っていればチヌは釣れます。
■底を切る
紀州釣りでチヌを狙って底を切る人はほとんどいないと思いますが、グレを狙う場合は底を切るのが一般的です。
少し底を切ってみると、ダンゴが割れた瞬間がとても分かりやすく、ダンゴ投入のテンポが良くなります。
グレを狙う場合は大きく底を切ることが多いですが、
たとえばグレ狙いで底を1~2ヒロほど切っていてもチヌが食い付くことがあります。
チヌが中層に浮いているような状況では、中層でダンゴを切ってサシエを落とし込んでみるのも面白いです。
アタリは道糸がスーッと走ったり、逆に止まったりするので、ウキ止めや道糸の動きでアタリを取ります。
チヌが中層に浮いている状況というのは普段でもよく見かけます。
たとえば夏場の高水温で海底が酸欠になっている時や、海が荒れて濁りが入っている状況なども中層は狙い目です。
また、水深のある釣場では、中層で釣れるチヌは型が良く、年無しクラスの大物も狙えます。
「紀州釣りは底をハワセないとチヌが釣れない」と思っている人がほとんどですが、そういう考えしか持っていない人には、「底を切ってチヌを釣る」というのがちょっと信じられないかもしれません。
また、岩場など底が粗い釣場では根がかり対策として少し底を切ります。
根がかり対策として底を切る場合、ダンゴは海底に届く直前に割れるように握り加減を調整します。
慣れるまではかなり難しいと思いますが、回数を重ねることで少しづつ握り加減やダンゴの水加減などが分かってきます。
■トントン
紀州釣りはダンゴの煙幕で海底にチヌを集めて釣りますが、トントンというのは紀州釣りでは最も基本的なタナ設定です。
ただ、トントンと言っても、実際には仕掛けが斜めになることがほとんどで、ウキ下は水深よりも少し長く取ることになります。
潮流や風の影響などで仕掛けが張って、ウキにダンゴのテンションがかかった状態を『トントン』と呼んでいます。
釣り始めは状況を見るためにトントンのタナに設定します。
トントンのメリットは、ダンゴが割れたタイミングが分かりやすく、魚のアタリが明確に出ることです。
エサ取りのアタリが明確に出ることで、空バリの状態で仕掛けを流すことも少なくなります。
また、タナをトントンにすることで、ハワセに比べ手返しが格段に早くなります。
チヌの活性が高い時は、サシエが少々浮いていてもバンバン食ってきますので、数釣りではトントンが有利です。
アタリが明確なので、チヌの硬い口に「掛け合わせる」事も可能になります。
■ハワセ釣り
ハワセ釣りとは、サシエを底に這わせたまま浮き上がらないように仕掛けを流すことです。
エサ取りが多い時、チヌの食いが渋い時などに多用します。
砂地以外では根掛かりが頻発しますので、波止や磯では海底が砂地のところまでダンゴを投げます。
ハワセ釣りの主な目的は2つです。
1、エサ取りが多い時、エサ取りにサシエが見つからないようにするためです。
基本的に落ちているエサというのは、エサ取りに強いです。エサ取りの大半は、海底より少し上にいるからです。
2、チヌの食いが渋い時、食い込みを良くするためです。
サシエを底に這わせることで、活性の低いチヌでも違和感なくサシエを食うため、食い込みが格段に良くなるというメリットがあります。
ハワセ釣りの釣り方ですが、基本的にハワセ釣りでは、どんな状況でもウキが常に海面より出でいる状態が正しいタナになります。
ダンゴの投入後ウキが海中に沈むようならウキ下を長くします。
ハワセと言うのは『ハリスを海底に這わせる』ということなのですが、実際にはハリスが全て海底に這っているという意味ではありません。
潮流や風などによって仕掛けが斜めになり、サシエサが浮き上ってしまうため、その分ウキ下を長めに取っておく、ということです。
ベタ凪の時では20cm程度のハワセで十分ですが、風や流れが強い時は1~2ヒロ、場合によっては3ヒロ以上もハワセる事もあります。
ハワセのメリットは、チヌの食い込みが良いのと、トントンの時ほどタナを気にしなくても、サシエの浮き上りを抑えられるという点です。
しかしあまり多くハワセすぎると、その分アタリが出にくくなります。
アタリが出にくいという事は、エサ取りのアタリも分からず、エサを取られたまま仕掛けをいつまでも流すことにもなります。
また、仕掛けを回収しようとリールを巻いたら勝手にチヌが釣れていた、という事にでもなると少し格好が悪いです。
実際にそういった経験をした人は多いですが、ハワセ過ぎが原因です。
できるだけチヌのアタリが分かる範囲でハワセるようにします。
基本的にハワセの場合、チヌがサシエを食って移動した時にウキにアタリが出ますので、居食いの時はアタリが出にくくなります。
もしアタリもなく勝手にチヌが釣れていた場合は、仕方がないので『違和感なく食わせたぞ!!』
とか言って、逆に自慢することです(笑)
まぁ、ハワセ釣りというのは元々それが狙いなので、間違ってはないです。
◎どれくらいのタナ設定が最適なのか?
たとえばハワセと言っても、どの程度はわせるのが良いのか、また、底を切る場合はどの程度なのか、トントンと言っても本当にサシエサが底まで届いているのかなど、正しいタナに設定することはとても難しいものです。
紀州釣りの正しいタナはその時々の条件で異なりますが、多くの経験を積むことで少しずつ解ってきます。
正しいタナとはチヌの食いが良く、はっきりとアタリが出るタナです。
潮流や風など、サシエサや仕掛けを浮き上らせたり、潮の干満によってタナを狂わせる要因があります。
しかし、どんな条件でも、常に正しいタナで紀州釣りをする事が釣果につながります。
これは言葉で習うより、まず実践して理解する事が大切かもしれません。
この記事へのコメント
コメント失礼します
紀州つりでダンゴを投げるまでにラインが穂先に絡んで遠投する時に割れたり、ラインをほどくのに時間がかかりすぎて、投げるテンポがドンドン悪くなってしまっています。
竿は5.3㍍の06号、鱗海AXです
インナーガイドを使わずトラブルなく紀州つりをしたいです。
なにか投げる前のコツやラインを絡ませないように注意するポイントを教えてください。お願い致します
紀州つりでダンゴを投げるまでにラインが穂先に絡んで遠投する時に割れたり、ラインをほどくのに時間がかかりすぎて、投げるテンポがドンドン悪くなってしまっています。
竿は5.3㍍の06号、鱗海AXです
インナーガイドを使わずトラブルなく紀州つりをしたいです。
なにか投げる前のコツやラインを絡ませないように注意するポイントを教えてください。お願い致します
くろだぃさん、こんにちは。
コメントありがとうございます。
穂先絡みについての質問ですね。いつも通りメッチャ答えが長いですが読んで下さい。
まず、穂先にラインが絡まる要因は2つ。竿や道糸などの道具と、投げる時の動作です。
穂先にほとんど絡まないように投げるコツがありますが、それはまた後ほど(笑)
まず、道具について。
道糸はヨレがあると穂先に絡みやすいので、ヨレのかかりにくい道糸を使用します。
色んな道糸がありますが、ヨレがかかりにくい道糸とヨレやすい道糸があります。
また、ヨレがかかっていても海水に馴染むとヨレが取れてしまう道糸もあります。
色々試してみて使いやすいものを選んで下さい。
竿は5.3メートルの06号とのことですが、紀州釣りでダンゴを遠投する場合、竿は長ければ長いほど、穂先が細ければ細いほどトラブルが多くなります。
私が紀州釣りで主に使用している竿は大島の1号4.5メートルで穂先は0.7ミリです。
この竿は穂先が細く、ラインが絡みやすいです。ラインが絡んだままダンゴを投げると簡単に折れてしまいます。
今まで4~5回は折ったと思います。
その経験から、現在は穂先を10センチほどカットして使っています。それに合わせてガイドも交換しました。
穂先をカットしたおかげで、穂先があまり回転しなくなり、絡みにくくなったと思います。
穂先をカットしてから20年以上使っていますが、それ以来1度も折っていません。
鱗海AXは穂先が0.8ミリなので、大島よりはマシだとは思いますが・・・。
私の知る限り、穂先をカットして使っている紀州釣り師は結構多いです。
もし折れたら試してみて下さい。
竿の長さですが、私の感じだと紀州釣りで5.3メートルは少し使いづらいのでは?と思います。
私は主に4.5ですが、短い竿に慣れてくると、もう長い竿には戻れません。
最近は短竿をよく使います。
状況によって、3.9とか3.6とか使ったりしますが、軽いし、扱いやすくて快適です。
ダンゴを投げる時のコツ。
穂先にほとんど絡まないように投げるコツについて。
文章で説明できるかどうか心配ですが、いってみましょう。
まず、ダンゴを杓に入れて右手で持ちます。
次にリールのベールを起こします。
左手で竿を持ちますが、この時、中指でスプールを押さえて余分なラインが出ないようにします。
余分な道糸が出てたるむと糸絡みの原因になります。
次に、杓を構えると同時に、穂先を下に向け、中指を緩めてスプールから少し道糸を出します。
この時、ウキを少し右側に飛ばして水面に浮かべておきます。
ただし、風が右から吹いている時は余分な道糸は出来るだけ出さず、張った状態でダンゴを投げます。
要するに、余分な道糸が絶対に左側には行かないようにするということです。
次に、ダンゴを投げる前に一度穂先を海面につけて竿をあおり、道糸がガイドに絡んでない事を確認します。
左手の中指はスプールを押さえたままですが、道糸がガイドに絡んでいると竿をあおっても道糸が出ようとしませんので、その道糸の張り具合を左手の中指で感じ取ります。
つまり、目視と左手の感触の2段構えで穂先絡みのチェックです。
もし絡んでたら、もう一度穂先を海面につけて竿をあおり、道糸を少し出してみる。
糸絡みが解消するまで数回繰り返す。(何度かやって解消しなければ手でほどく)
次に、ダンゴを投げるまでと、投げる時、穂先は必ず下に向けておきます。
穂先を上に向けると絡みやすくなりますので厳禁です。
穂先を下げた状態をキープしてダンゴを投げます。
ダンゴを投げた瞬間に左手の中指を離しますが、同時に穂先が空中のダンゴを追うような感じで竿を少し左側に振り、同時にウキや道糸と穂先が重ならないように穂先を退避させます。
以上がコツです。分かりづらいと思いますが、要点は、
1、竿は左側なのでウキと余分な道糸は常に右側をキープ。
2、糸絡みを目視と指の感触でキャッチ。
3、穂先を海面につけて糸絡みを取る。
4、穂先は常に下を向ける。
5、ダンゴを投げる時は穂先を退避させる。
まぁ、こんな感じで私の場合、糸絡みはほぼゼロです。
というか、ダンゴを全力で投げると、糸絡み=穂先即アウトですので。
慣れれば一連の動作が全て癖になりますので、体で覚えるように何度も練習してみてください。
コメントありがとうございます。
穂先絡みについての質問ですね。いつも通りメッチャ答えが長いですが読んで下さい。
まず、穂先にラインが絡まる要因は2つ。竿や道糸などの道具と、投げる時の動作です。
穂先にほとんど絡まないように投げるコツがありますが、それはまた後ほど(笑)
まず、道具について。
道糸はヨレがあると穂先に絡みやすいので、ヨレのかかりにくい道糸を使用します。
色んな道糸がありますが、ヨレがかかりにくい道糸とヨレやすい道糸があります。
また、ヨレがかかっていても海水に馴染むとヨレが取れてしまう道糸もあります。
色々試してみて使いやすいものを選んで下さい。
竿は5.3メートルの06号とのことですが、紀州釣りでダンゴを遠投する場合、竿は長ければ長いほど、穂先が細ければ細いほどトラブルが多くなります。
私が紀州釣りで主に使用している竿は大島の1号4.5メートルで穂先は0.7ミリです。
この竿は穂先が細く、ラインが絡みやすいです。ラインが絡んだままダンゴを投げると簡単に折れてしまいます。
今まで4~5回は折ったと思います。
その経験から、現在は穂先を10センチほどカットして使っています。それに合わせてガイドも交換しました。
穂先をカットしたおかげで、穂先があまり回転しなくなり、絡みにくくなったと思います。
穂先をカットしてから20年以上使っていますが、それ以来1度も折っていません。
鱗海AXは穂先が0.8ミリなので、大島よりはマシだとは思いますが・・・。
私の知る限り、穂先をカットして使っている紀州釣り師は結構多いです。
もし折れたら試してみて下さい。
竿の長さですが、私の感じだと紀州釣りで5.3メートルは少し使いづらいのでは?と思います。
私は主に4.5ですが、短い竿に慣れてくると、もう長い竿には戻れません。
最近は短竿をよく使います。
状況によって、3.9とか3.6とか使ったりしますが、軽いし、扱いやすくて快適です。
ダンゴを投げる時のコツ。
穂先にほとんど絡まないように投げるコツについて。
文章で説明できるかどうか心配ですが、いってみましょう。
まず、ダンゴを杓に入れて右手で持ちます。
次にリールのベールを起こします。
左手で竿を持ちますが、この時、中指でスプールを押さえて余分なラインが出ないようにします。
余分な道糸が出てたるむと糸絡みの原因になります。
次に、杓を構えると同時に、穂先を下に向け、中指を緩めてスプールから少し道糸を出します。
この時、ウキを少し右側に飛ばして水面に浮かべておきます。
ただし、風が右から吹いている時は余分な道糸は出来るだけ出さず、張った状態でダンゴを投げます。
要するに、余分な道糸が絶対に左側には行かないようにするということです。
次に、ダンゴを投げる前に一度穂先を海面につけて竿をあおり、道糸がガイドに絡んでない事を確認します。
左手の中指はスプールを押さえたままですが、道糸がガイドに絡んでいると竿をあおっても道糸が出ようとしませんので、その道糸の張り具合を左手の中指で感じ取ります。
つまり、目視と左手の感触の2段構えで穂先絡みのチェックです。
もし絡んでたら、もう一度穂先を海面につけて竿をあおり、道糸を少し出してみる。
糸絡みが解消するまで数回繰り返す。(何度かやって解消しなければ手でほどく)
次に、ダンゴを投げるまでと、投げる時、穂先は必ず下に向けておきます。
穂先を上に向けると絡みやすくなりますので厳禁です。
穂先を下げた状態をキープしてダンゴを投げます。
ダンゴを投げた瞬間に左手の中指を離しますが、同時に穂先が空中のダンゴを追うような感じで竿を少し左側に振り、同時にウキや道糸と穂先が重ならないように穂先を退避させます。
以上がコツです。分かりづらいと思いますが、要点は、
1、竿は左側なのでウキと余分な道糸は常に右側をキープ。
2、糸絡みを目視と指の感触でキャッチ。
3、穂先を海面につけて糸絡みを取る。
4、穂先は常に下を向ける。
5、ダンゴを投げる時は穂先を退避させる。
まぁ、こんな感じで私の場合、糸絡みはほぼゼロです。
というか、ダンゴを全力で投げると、糸絡み=穂先即アウトですので。
慣れれば一連の動作が全て癖になりますので、体で覚えるように何度も練習してみてください。
返信ありがとうございます!
4.2㍍の磯竿も持っているので、多様してみようとおもいます!
ありがとうございました!
4.2㍍の磯竿も持っているので、多様してみようとおもいます!
ありがとうございました!
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。