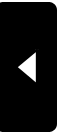紀州釣りの釣りスタイルを考える
紀州釣りを長年やっていると、紀州釣りの釣りスタイルって、人それぞれで違うものなんだなと実感します。
それもそのはずで、人によって仕掛けの太さやウキの大きさ、ダンゴの配合や握り方などさまざまで、紀州釣りを長くやればやるほど、その人に合った釣り方に自然となっていくのかな、と思ったりします。
それでも紀州釣りには大きく分けて2つのスタイルにたどり着くと私は考えています。
ひとつはブッ込みスタイル、もうひとつはフカセスタイルです。
実はこれらの釣り方を釣り場やその時の状況に応じて使い分けることで、釣果はアップします。

まずはブッ込みスタイルですが、ブッ込みスタイルというのは、とにかく仕掛けを底に這わせてサシエを安定させる事に主眼を置く釣り方です。
水深の浅い釣り場に適していますが、水深のある釣場でも実績があります。
この釣り方をする人というのは実はかなり多いです。
水深の浅い釣場というのは、一般的にタナ合わせを比較的容易に行うことができます。
ところが、釣り場では状況がコロコロ変わります。
風が強くなったり、流れが速くなったりと、あまりにも変化が多い状況では正確なタナ合わせが非常に難しくなってきます。
タナを合わせるのが難しいのであれば、無理にタナを合わせず、ウキ下を余分に取っておいて仕掛けをハワセ気味にしてやるのが無難です。
特に河口周辺などは流れが速いです。
浅い釣場で流れが速い時は、大きくハワセていても魚のアタリは明確に出ます。
また、多めにハワセないとなかなか食ってこないことも多いです。
ハワセ釣りのデメリットは、ダンゴが割れたタイミングが分かりづらい事ですが、このような浅い釣り場では、メリットの方が大きいのでハワセ釣りの方が好釣果に恵まれることが多いです。
一方、深場でのブッ込みスタイルについてですが、例えば8ヒロ~10ヒロもある釣り場でハワセ釣りをしようとしても、なかなかうまくいきません。
流れのない時は、8ヒロのタナに対し10ヒロ取れば仕掛けが這うかもしれませんが、一旦流れ出すとそうはいきません。
こんな水深で本当に仕掛けを底に這わそうと思えば、8ヒロのタナに対し20ヒロくらい取らなければならなくなります。
現実的にそんなタナには設定できませんので、無理に仕掛けを這わそうと思えば、サスペンドラインでウキを取っ払うか、ハリスにオモリを打つしか方法はありません。
実際、8ヒロのタナに対し10ヒロ取っておいて、さらに状況に応じてオモリを打つ、というのが深場でのブッ込みスタイルです。
道糸は風の抵抗を受けないサスペンドラインを使い、サシエは動かさず、チヌが食い付くのをゆっくり待ちます。
私は、このオモリを打つ、という釣り方が実は好きではありません。
しかし、低水温時や春先の大型狙いなど、この釣り方の方が釣果が上がる時もあります。
また、この釣り方を得意としている方も結構おられます。
ところで、私は筏のかかり釣りもやりますが、この時は道糸とハリスはフロロカーボンの通しなのでオモリを付けなくても結構ハワセやすいです。
フロロカーボンの比重は1.78、ナイロンは1.14です。
紀州釣りでも道糸をフロロカーボンにすればハワセやすいのですが、アタリが分かりにくいのと根掛りが多くなるし、巻き替えが面倒なので私は使いません。
強風時や激流など、どうしても仕掛け全体をハワセて1匹でも釣りたい時もあると思いますが、そんな場合は一度試してみてはいかがでしょう。
一方、フカセスタイルの紀州釣りについてです。
これは浅場から深場までオールラウンドに使える釣り方だと思っています。
フカセスタイルというのは、基本的に潮に合わせて仕掛けを流し込んでいくような釣り方です。
仕掛けの流し方ですが、ダンゴから出た煙幕の筋に沿って仕掛けを流し、サシエを送り込んでやります。
この時、いかに正確に撒き餌の筋に乗せて流せるかどうかが釣果を左右します。
撒き餌の筋から離れるとチヌはまず釣れません。
一般的なフカセ釣りと同様に、サシエ先行で底スレスレに仕掛けを流すのがコツですので、道糸が先行しないようにタナは底トントン~20センチ程度のハワセでダンゴを打ち返します。
サシエは浮き上がらないように注意します。
仕掛けについては、道糸が負荷にならないようにフロートタイプのものを使います。
道糸を水面に浮かべておき、サシエの後をついていくようなイメージで仕掛けを操作します。
サスペンドラインでは道糸が潮に乗ってしまい、このようなラインコントロールができませんので、フカセスタイルの紀州釣りには適していません。
また、この操作はダンゴが割れる前に完了しておくことが重要で、ダンゴが割れてから仕掛けを引っ張るとサシエが浮き上がったり、大きく移動してしまう原因になります。
ウキは風や潮の抵抗が少ない寝ウキを使います。
フカセスタイルの紀州釣りでは、仕掛けを流し込む以外に、潮の流れがゆっくりの時は縦方向の誘いにも効果があります。
ダンゴが割れた瞬間が分かるようにタナ設定しておくことで、チヌがダンゴを突ついたり、サシエを吸い込んだ瞬間のアタリが分かります。
また、チヌが反転してウキが消し込まれるまでの様子がはっきり見えて楽しめます。
紀州釣りではダンゴが割れてすぐにチヌが釣れることがかなり多いのですが、それがこの釣り方で手に取るように分かります。
今回はブッ込みスタイルとフカセスタイルについて書きましたが、実際はその中間的なスタイルで釣りをする場合が多いです。
それは、潮の流れや風の影響で食いが悪くなったり、アタリが出にくい時などです。
ブッ込みスタイルでタナを詰めた場合や、フカセスタイルでハワセ幅を多めに取った場合などは中間的なスタイルとなり、それぞれのデメリットを消去したい時に使います。
基本的な考え方として、
ブッ込みスタイル = サシエを動かさない。海底をズル引き。食い込みが良い。
フカセスタイル = サシエを動かす。潮に乗せて流す。アタリが出やすい。
といった感じなのですが、ご理解いただけたでしょうか。
それもそのはずで、人によって仕掛けの太さやウキの大きさ、ダンゴの配合や握り方などさまざまで、紀州釣りを長くやればやるほど、その人に合った釣り方に自然となっていくのかな、と思ったりします。
それでも紀州釣りには大きく分けて2つのスタイルにたどり着くと私は考えています。
ひとつはブッ込みスタイル、もうひとつはフカセスタイルです。
実はこれらの釣り方を釣り場やその時の状況に応じて使い分けることで、釣果はアップします。
まずはブッ込みスタイルですが、ブッ込みスタイルというのは、とにかく仕掛けを底に這わせてサシエを安定させる事に主眼を置く釣り方です。
水深の浅い釣り場に適していますが、水深のある釣場でも実績があります。
この釣り方をする人というのは実はかなり多いです。
水深の浅い釣場というのは、一般的にタナ合わせを比較的容易に行うことができます。
ところが、釣り場では状況がコロコロ変わります。
風が強くなったり、流れが速くなったりと、あまりにも変化が多い状況では正確なタナ合わせが非常に難しくなってきます。
タナを合わせるのが難しいのであれば、無理にタナを合わせず、ウキ下を余分に取っておいて仕掛けをハワセ気味にしてやるのが無難です。
特に河口周辺などは流れが速いです。
浅い釣場で流れが速い時は、大きくハワセていても魚のアタリは明確に出ます。
また、多めにハワセないとなかなか食ってこないことも多いです。
ハワセ釣りのデメリットは、ダンゴが割れたタイミングが分かりづらい事ですが、このような浅い釣り場では、メリットの方が大きいのでハワセ釣りの方が好釣果に恵まれることが多いです。
一方、深場でのブッ込みスタイルについてですが、例えば8ヒロ~10ヒロもある釣り場でハワセ釣りをしようとしても、なかなかうまくいきません。
流れのない時は、8ヒロのタナに対し10ヒロ取れば仕掛けが這うかもしれませんが、一旦流れ出すとそうはいきません。
こんな水深で本当に仕掛けを底に這わそうと思えば、8ヒロのタナに対し20ヒロくらい取らなければならなくなります。
現実的にそんなタナには設定できませんので、無理に仕掛けを這わそうと思えば、サスペンドラインでウキを取っ払うか、ハリスにオモリを打つしか方法はありません。
実際、8ヒロのタナに対し10ヒロ取っておいて、さらに状況に応じてオモリを打つ、というのが深場でのブッ込みスタイルです。
道糸は風の抵抗を受けないサスペンドラインを使い、サシエは動かさず、チヌが食い付くのをゆっくり待ちます。
私は、このオモリを打つ、という釣り方が実は好きではありません。
しかし、低水温時や春先の大型狙いなど、この釣り方の方が釣果が上がる時もあります。
また、この釣り方を得意としている方も結構おられます。
ところで、私は筏のかかり釣りもやりますが、この時は道糸とハリスはフロロカーボンの通しなのでオモリを付けなくても結構ハワセやすいです。
フロロカーボンの比重は1.78、ナイロンは1.14です。
紀州釣りでも道糸をフロロカーボンにすればハワセやすいのですが、アタリが分かりにくいのと根掛りが多くなるし、巻き替えが面倒なので私は使いません。
強風時や激流など、どうしても仕掛け全体をハワセて1匹でも釣りたい時もあると思いますが、そんな場合は一度試してみてはいかがでしょう。
一方、フカセスタイルの紀州釣りについてです。
これは浅場から深場までオールラウンドに使える釣り方だと思っています。
フカセスタイルというのは、基本的に潮に合わせて仕掛けを流し込んでいくような釣り方です。
仕掛けの流し方ですが、ダンゴから出た煙幕の筋に沿って仕掛けを流し、サシエを送り込んでやります。
この時、いかに正確に撒き餌の筋に乗せて流せるかどうかが釣果を左右します。
撒き餌の筋から離れるとチヌはまず釣れません。
一般的なフカセ釣りと同様に、サシエ先行で底スレスレに仕掛けを流すのがコツですので、道糸が先行しないようにタナは底トントン~20センチ程度のハワセでダンゴを打ち返します。
サシエは浮き上がらないように注意します。
仕掛けについては、道糸が負荷にならないようにフロートタイプのものを使います。
道糸を水面に浮かべておき、サシエの後をついていくようなイメージで仕掛けを操作します。
サスペンドラインでは道糸が潮に乗ってしまい、このようなラインコントロールができませんので、フカセスタイルの紀州釣りには適していません。
また、この操作はダンゴが割れる前に完了しておくことが重要で、ダンゴが割れてから仕掛けを引っ張るとサシエが浮き上がったり、大きく移動してしまう原因になります。
ウキは風や潮の抵抗が少ない寝ウキを使います。
フカセスタイルの紀州釣りでは、仕掛けを流し込む以外に、潮の流れがゆっくりの時は縦方向の誘いにも効果があります。
ダンゴが割れた瞬間が分かるようにタナ設定しておくことで、チヌがダンゴを突ついたり、サシエを吸い込んだ瞬間のアタリが分かります。
また、チヌが反転してウキが消し込まれるまでの様子がはっきり見えて楽しめます。
紀州釣りではダンゴが割れてすぐにチヌが釣れることがかなり多いのですが、それがこの釣り方で手に取るように分かります。
今回はブッ込みスタイルとフカセスタイルについて書きましたが、実際はその中間的なスタイルで釣りをする場合が多いです。
それは、潮の流れや風の影響で食いが悪くなったり、アタリが出にくい時などです。
ブッ込みスタイルでタナを詰めた場合や、フカセスタイルでハワセ幅を多めに取った場合などは中間的なスタイルとなり、それぞれのデメリットを消去したい時に使います。
基本的な考え方として、
ブッ込みスタイル = サシエを動かさない。海底をズル引き。食い込みが良い。
フカセスタイル = サシエを動かす。潮に乗せて流す。アタリが出やすい。
といった感じなのですが、ご理解いただけたでしょうか。
この記事へのコメント
釣行釣果は無いのですか?
うんちくが多すぎです。
長い杓の方が扱いやすく
良く飛ぶとは限りません。
私も長杓を以前は使用していましたが
短い杓でも余り飛距離が
変わらない事に気付きました。
勿論30~40mが投点です。
うんちくが多すぎです。
長い杓の方が扱いやすく
良く飛ぶとは限りません。
私も長杓を以前は使用していましたが
短い杓でも余り飛距離が
変わらない事に気付きました。
勿論30~40mが投点です。
和歌山の紀州釣り師さん、辛口のコメントをありがとうございます。
> 釣行釣果は無いのですか?
ありません。釣行記ブログではなく、ノウハウ系のブログ構成となっています。
>うんちくが多すぎです。
ノウハウ系のブログですので仕方ありません。
説明文が足りないと誤解されやすいので、できるだけ細かいところまで気を配って文章を書くように心がけています。
このようなサイトを他でも10年以上やっていますが、説明文が足りないせいで質問攻めに合ったことが何度もあります。
紀州釣りの細かい部分の考え方や経験は人それぞれで違いますので、同じ文章でもどう受け取るかは本人次第という事が多々あります。
内容を楽しめる人だけ当ブログを見て頂けたらと思っています。
>長い杓の方が扱いやすく 良く飛ぶとは限りません。
それはそうです。杓の性能や自分の腕力、握力なども関係してきますね。
短い杓を使っている友人がいて、風の強い日に糸がらみが頻発していたので、長い杓を勧めたところ糸がらみが解消しました。
そのような経験から「長い杓の方が扱いやすい」という表現になりました。
竿の長さでも同じことが言えると思いますが、何事もケースバイケース、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」という感じに捉えて頂けると幸いです。
>私も長杓を以前は使用していましたが 短い杓でも余り飛距離が 変わらない事に気付きました。
自分に合った杓を使われるのが一番だと思います。
私は自作の杓を30~40本ほど持っていますが、1本1本、全て性格が違いますね。
人からもらったものは、やはり自分には合わないです。
>勿論30~40mが投点です。
距離よりもコントロールが重要ですので、自分が扱いやすいと思う杓を使うのが一番だと思います。
私は自分に合わない杓を使って遠投を繰り返し、肩を壊した経験があります。
30~40mは十分遠投の部類に入ると思いますが、無理をして肩を壊さないように気を付けてこれからも紀州釣りを楽しんで下さい。
このブログをご覧のみなさんも気を付けて下さいね。
> 釣行釣果は無いのですか?
ありません。釣行記ブログではなく、ノウハウ系のブログ構成となっています。
>うんちくが多すぎです。
ノウハウ系のブログですので仕方ありません。
説明文が足りないと誤解されやすいので、できるだけ細かいところまで気を配って文章を書くように心がけています。
このようなサイトを他でも10年以上やっていますが、説明文が足りないせいで質問攻めに合ったことが何度もあります。
紀州釣りの細かい部分の考え方や経験は人それぞれで違いますので、同じ文章でもどう受け取るかは本人次第という事が多々あります。
内容を楽しめる人だけ当ブログを見て頂けたらと思っています。
>長い杓の方が扱いやすく 良く飛ぶとは限りません。
それはそうです。杓の性能や自分の腕力、握力なども関係してきますね。
短い杓を使っている友人がいて、風の強い日に糸がらみが頻発していたので、長い杓を勧めたところ糸がらみが解消しました。
そのような経験から「長い杓の方が扱いやすい」という表現になりました。
竿の長さでも同じことが言えると思いますが、何事もケースバイケース、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」という感じに捉えて頂けると幸いです。
>私も長杓を以前は使用していましたが 短い杓でも余り飛距離が 変わらない事に気付きました。
自分に合った杓を使われるのが一番だと思います。
私は自作の杓を30~40本ほど持っていますが、1本1本、全て性格が違いますね。
人からもらったものは、やはり自分には合わないです。
>勿論30~40mが投点です。
距離よりもコントロールが重要ですので、自分が扱いやすいと思う杓を使うのが一番だと思います。
私は自分に合わない杓を使って遠投を繰り返し、肩を壊した経験があります。
30~40mは十分遠投の部類に入ると思いますが、無理をして肩を壊さないように気を付けてこれからも紀州釣りを楽しんで下さい。
このブログをご覧のみなさんも気を付けて下さいね。
初めましてm(__)m
フカセスタイルについてですが
ダンゴは着底させてそんなにもたせず、少し底を切る位で流すイメージでよろしいでしょうか?
それとも着底前にダンゴが割れて流すイメージでしょうか?
エサとりの量ととサシエサも重要になりそうですね。
フカセスタイルについてですが
ダンゴは着底させてそんなにもたせず、少し底を切る位で流すイメージでよろしいでしょうか?
それとも着底前にダンゴが割れて流すイメージでしょうか?
エサとりの量ととサシエサも重要になりそうですね。
コメントありがとうございます。
フカセスタイルついてのご質問ですね。
> ダンゴは着底させてそんなにもたせず、少し底を切る位で流すイメージでよろしいでしょうか?
ダンゴの割れるタイミングですが、仕掛けが潮にうまく馴染んでから割れないと仕掛けがダンゴの濁りの帯から外れてしまいますので、ある程度の時間はもたせるようにします。
実はこのタイミングは非常に重要です。
ダンゴには、仕掛けが潮に馴染むまで割れずに我慢してもらうのですが、仕掛けが馴染んだ後は早く割れてもらわないと、どんどん糸フケが大きくなって濁りの帯から外れやすくなってしまいます。
もしダンゴがなかなか割れず糸フケが大きくなりそうな時は、ダンゴが割れるまでラインメンディングを何度も繰り返して糸フケを最小限に抑えるということをします。
流す時のタナについては底を切らず、底スレスレから20cmのハワセをイメージしますが、多少浮き上がってもそれが誘いになってチヌは食ってきます。
海底を少し這っている方がチヌがサシエサを食いやすいのですが、半ヒロ以上ハワセるとダンゴの帯から外れやすくなります。
筏のかかり釣りをイメージし、できるだけダンゴの真上近くにウキがある方が、ダンゴ濁りの帯から外れにくいというのが発想の原点です。
> それとも着底前にダンゴが割れて流すイメージでしょうか?
着底前に割れてもチヌが釣れることがありますが、着底させてポイントを作るのがダンゴの役割なので、途中で割れないようにしっかり握ります。
出来れば海底にいるチヌやエサ取り、ボラなどにダンゴを割ってもらうのが理想です。
> エサとりの量とサシエサも重要になりそうですね。
エサ取りが多い時はダンゴの割れを遅くして、チヌがダンゴの近くに入ってくるための時間稼ぎをします。
また、サシエサは底を這うようなイメージで流すことで、エサ取りに取られにくくなります。
サシエサはチヌの食いを最優先して選びます。サシエサでエサ取りをかわすという発想よりも、チヌを寄せてエサ取りを蹴散らしてもらう方が圧倒的に釣りやすいです。
紀州釣りのフカセスタイルについては、ダンゴが割れてからサシエサが無くなるまでのわずかな時間に、いかにチヌに食わせるか、というのが課題になると思います。
流し方が正しければチヌが釣れますが、間違っているとエサ取りが釣れてしまいます。
そして重要なことは、一日中同じ釣り方、ワンパターンでは好釣果は望めないということです。
チヌは変化に弱い魚だと言われていますが、刻一刻と変化する状況に合わせて、フカセスタイルやブッコミスタイル、その中間的はスタイルも併用して、色んな変化を試してみることが好釣果につながります。
紀州釣り歴三年というのは、ちょうど私がこの釣りに開眼した頃で、最も成長著しい時期だったと思います。
これからもどんどん釣果を伸ばして、紀州釣りを楽しんで下さい。
フカセスタイルついてのご質問ですね。
> ダンゴは着底させてそんなにもたせず、少し底を切る位で流すイメージでよろしいでしょうか?
ダンゴの割れるタイミングですが、仕掛けが潮にうまく馴染んでから割れないと仕掛けがダンゴの濁りの帯から外れてしまいますので、ある程度の時間はもたせるようにします。
実はこのタイミングは非常に重要です。
ダンゴには、仕掛けが潮に馴染むまで割れずに我慢してもらうのですが、仕掛けが馴染んだ後は早く割れてもらわないと、どんどん糸フケが大きくなって濁りの帯から外れやすくなってしまいます。
もしダンゴがなかなか割れず糸フケが大きくなりそうな時は、ダンゴが割れるまでラインメンディングを何度も繰り返して糸フケを最小限に抑えるということをします。
流す時のタナについては底を切らず、底スレスレから20cmのハワセをイメージしますが、多少浮き上がってもそれが誘いになってチヌは食ってきます。
海底を少し這っている方がチヌがサシエサを食いやすいのですが、半ヒロ以上ハワセるとダンゴの帯から外れやすくなります。
筏のかかり釣りをイメージし、できるだけダンゴの真上近くにウキがある方が、ダンゴ濁りの帯から外れにくいというのが発想の原点です。
> それとも着底前にダンゴが割れて流すイメージでしょうか?
着底前に割れてもチヌが釣れることがありますが、着底させてポイントを作るのがダンゴの役割なので、途中で割れないようにしっかり握ります。
出来れば海底にいるチヌやエサ取り、ボラなどにダンゴを割ってもらうのが理想です。
> エサとりの量とサシエサも重要になりそうですね。
エサ取りが多い時はダンゴの割れを遅くして、チヌがダンゴの近くに入ってくるための時間稼ぎをします。
また、サシエサは底を這うようなイメージで流すことで、エサ取りに取られにくくなります。
サシエサはチヌの食いを最優先して選びます。サシエサでエサ取りをかわすという発想よりも、チヌを寄せてエサ取りを蹴散らしてもらう方が圧倒的に釣りやすいです。
紀州釣りのフカセスタイルについては、ダンゴが割れてからサシエサが無くなるまでのわずかな時間に、いかにチヌに食わせるか、というのが課題になると思います。
流し方が正しければチヌが釣れますが、間違っているとエサ取りが釣れてしまいます。
そして重要なことは、一日中同じ釣り方、ワンパターンでは好釣果は望めないということです。
チヌは変化に弱い魚だと言われていますが、刻一刻と変化する状況に合わせて、フカセスタイルやブッコミスタイル、その中間的はスタイルも併用して、色んな変化を試してみることが好釣果につながります。
紀州釣り歴三年というのは、ちょうど私がこの釣りに開眼した頃で、最も成長著しい時期だったと思います。
これからもどんどん釣果を伸ばして、紀州釣りを楽しんで下さい。
丁寧な回答を頂き嬉しく思いますm(__)m
これからの釣行の参考に致します。
また分からないことはコメントさせて下さい。
このブログ楽しみにしております。
これからの釣行の参考に致します。
また分からないことはコメントさせて下さい。
このブログ楽しみにしております。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。