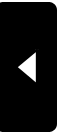筏かかり釣りから紀州釣りを学ぶ
お正月に筏のかかり釣りに行ってきました。南紀白浜堅田の筏で、実寸53cmの年無しを含め、45cm前後をメインに5匹のチヌが釣れました。
一番小さいのが26cmです。親子というか、同じ魚とは思えません(笑)

当日、私を含め44名の方が筏に上られ、全体でチヌ9匹という釣果でした。
今回はクジ運よく、連日年無しが上がっている筏に乗ることができ、好釣果を得ることができました。
今回、このような好釣果に恵まれたもうひとつの理由は、紀州釣りのノウハウが大きく役立ったということです。
かかり釣りというのは、紀州釣りと同じようにダンゴでチヌを釣る釣法ですので、基本的な考え方は紀州釣りと全く同じです。
磯や波止からウキを付けて磯竿とスピニングリールでやるのが紀州釣り、
筏やカセでウキを付けずに短竿と片軸または両軸リールでやるのがかかり釣りです。
道具立てやフィールドは違っても、どちらもダンゴを巧みに操ってチヌを寄せて釣る釣り方という点では同じです。
私は今では紀州釣り以外の釣りはほとんどやりませんが、筏のかかり釣りからは学ぶことが非常に多いので、今回はそのあたりをテーマに考えてみたいと思います。
1、サシエは浮かせてはいけないのか?
サシエは底ベタが基本ですが、時と場合によります。
筏釣りの場合、海底で魚の反応がない時が多々あります。
そんな時は、サシエを海底から引っ張り上げてからゆっくり落とし込んで魚の反応を見ます。
それを数回やってみるとチヌが食ってくることが結構あります。
今回の筏釣りでは真冬の低水温ということもあり、上で食ってくるのはほとんどがマダイかチャリコでしたが、そのまま落とし込んでサシエが着底するとチヌが食ってきました。
2、ダンゴは着底後、すぐに割れないといけないのか?
筏釣りではダンゴ着底後すぐに割れるように調整するのは、紀州釣りに比べ簡単です。
紀州釣りの場合も筏釣り同様、ダンゴ打ち返しのリズムがあるので、チヌを寄せる段階で流れの速い時などはできるだけ早く割れた方がチヌを寄せやすいです。
とは言っても、ダンゴを杓で遠投する時の圧力や着水時の衝撃でも割れずに海底まで届くダンゴにしないといけないので、そのへんの調整が難しいです。
ところで、チヌがダンゴの近くに寄って来ているような段階では、チヌにダンゴを割らせる事が非常に重要なので、自然にバラケたり、沈下途中エサ取りやボラに割られない硬さのダンゴにしないといけません。
アミエビをアンコにするとダンゴへの反応が良くなるので、チヌにダンゴを割らせたい時は特に有効です。
今回の筏釣りでは、ダンゴの中にアミエビとつぶしたオキアミ、サナギミンチ激荒などをアンコにしてチヌに割らせる作戦にしました。
ダンゴへの反応は良かったのですが、ダンゴが割れるまで時間がかかるときはチヌは釣れませんでした。
逆にすぐにダンゴが割れる時は、道糸をゆるめてしばらく待っているとチヌが食ってきました。
低水温時はチヌがダンゴに触ってくる回数が少ないので、できるだけ割れやすいダンゴの方が釣果につながると感じました。
また、サシエをダンゴに包まず外に出しておくと、いきなりサシエを食ってくることがありますので、ダンゴには反応があるけれども、なかなかサシエを食って来ないような時は試してみて下さい。
3、サシエサのローテーションは有効か?
紀州釣りではいつもボケをメインに使っています。
ボケに勝るエサはないと思っているので、どんな時でもボケを使って釣行します。
ボケで食わない時は何に変えても食って来ないうえに、オキアミではアタリすらなくエサ取りに取られることが多いので、私の中では「オキアミは使いにくいエサ」という印象があります。
そのような理由から、オキアミやコーンは予備に持って行く程度でメインとしては使いません。
一方、筏釣りでもメインとなるのは何と言ってもボケです。
ところが、同じエサを何度も使っていると魚の反応が悪くなることがあります。
ボケに勝るエサはないはずなのに、チヌが見向きもしなくなるという現象が起こります。
筏では波止と違い、毎日大量にマキエをしている分、お腹がいっぱいで食い渋りという現象が起こるのでは、と考えます。
ボケで反応がない時はオキアミにスイッチしたり、コーンやサナギに変えたりして目先を変えてみると突然食ってくることがあります。
今回はカニやカメジャコといった少し固めのエサに変えると反応が良かったと思います。
食い込みの点ではオキアミでもあまり変わらないと思いますので、オキアミをメインに使ってローテーションしても大丈夫だと思います。
そして、チヌの反応を見るという点でもサシエサはある程度ローテーションした方が釣果につながるのではと感じました。
4、ハワセ釣りは有効か?
紀州釣りではハワセ釣りの方がチヌの食い込みもよく、非常に有効な釣り方です。
ただし、ハワセ釣りは打ち返しのリズムが悪くなるという欠点を併せ持ちますので、チヌを寄せるために大きめのダンゴにするか、追加のダンゴを打つなどの工夫が必要です。
しかし、流れや風のある時に正確にポイントへ追加のダンゴを打つのは困難です。
よく、ウキの上に追加のダンゴを打っている人を見かけますが、ハワセている分、ウキの直下にはサシエはありませんし、ウキが流れる方向とダンゴの濁りが流れる方向が同じでないため、チヌを寄せるどころかチヌを分散させて他人のためにマキエをしているような状態になり逆効果です。
ウキとサシエ、ダンゴの濁りが同じ方向に流れるタナ設定にしないとチヌは釣れませんので、ハワセ幅は最小限で、というのが紀州釣りでは釣りやすいのではないでしょうか。
一方、筏釣りでは竿下を釣りますので、追加のダンゴをどんどん落としてポイントを確立していくことが容易にできます。
ハリスはハワセた方がチヌの食い込みが良いので、ハワセてアタリを待ちます。その後さらに流れた分だけ余分に道糸を送り込むことで、少し離れたところにいるチヌを狙うこともできます。
サシエが流れて行く方向は潮下であり、ダンゴの濁りが流れて行く方向と同じなので、ハワセ幅は無限大で、極端な話、何十メートルハワセても問題ありません。
紀州釣りでも筏のかかり釣りでも、サシエとダンゴの濁りを同調させることは非常に重要で、好釣果を得るための最大のテーマと言えるでしょう。

ちなみに今回の筏かかり釣りのタックルは、
竿:SHIMANO 18セイハコウフィラート160 先調子8:2
リール:SHIMANO セイハコウ60スペシャル RED
道糸、ハリス: VARIBAS筏かかり フロロカーボン2号通し
ハリ:OWNER スーパー競技チヌ3号でした。
一番小さいのが26cmです。親子というか、同じ魚とは思えません(笑)
当日、私を含め44名の方が筏に上られ、全体でチヌ9匹という釣果でした。
今回はクジ運よく、連日年無しが上がっている筏に乗ることができ、好釣果を得ることができました。
今回、このような好釣果に恵まれたもうひとつの理由は、紀州釣りのノウハウが大きく役立ったということです。
かかり釣りというのは、紀州釣りと同じようにダンゴでチヌを釣る釣法ですので、基本的な考え方は紀州釣りと全く同じです。
磯や波止からウキを付けて磯竿とスピニングリールでやるのが紀州釣り、
筏やカセでウキを付けずに短竿と片軸または両軸リールでやるのがかかり釣りです。
道具立てやフィールドは違っても、どちらもダンゴを巧みに操ってチヌを寄せて釣る釣り方という点では同じです。
私は今では紀州釣り以外の釣りはほとんどやりませんが、筏のかかり釣りからは学ぶことが非常に多いので、今回はそのあたりをテーマに考えてみたいと思います。
1、サシエは浮かせてはいけないのか?
サシエは底ベタが基本ですが、時と場合によります。
筏釣りの場合、海底で魚の反応がない時が多々あります。
そんな時は、サシエを海底から引っ張り上げてからゆっくり落とし込んで魚の反応を見ます。
それを数回やってみるとチヌが食ってくることが結構あります。
今回の筏釣りでは真冬の低水温ということもあり、上で食ってくるのはほとんどがマダイかチャリコでしたが、そのまま落とし込んでサシエが着底するとチヌが食ってきました。
2、ダンゴは着底後、すぐに割れないといけないのか?
筏釣りではダンゴ着底後すぐに割れるように調整するのは、紀州釣りに比べ簡単です。
紀州釣りの場合も筏釣り同様、ダンゴ打ち返しのリズムがあるので、チヌを寄せる段階で流れの速い時などはできるだけ早く割れた方がチヌを寄せやすいです。
とは言っても、ダンゴを杓で遠投する時の圧力や着水時の衝撃でも割れずに海底まで届くダンゴにしないといけないので、そのへんの調整が難しいです。
ところで、チヌがダンゴの近くに寄って来ているような段階では、チヌにダンゴを割らせる事が非常に重要なので、自然にバラケたり、沈下途中エサ取りやボラに割られない硬さのダンゴにしないといけません。
アミエビをアンコにするとダンゴへの反応が良くなるので、チヌにダンゴを割らせたい時は特に有効です。
今回の筏釣りでは、ダンゴの中にアミエビとつぶしたオキアミ、サナギミンチ激荒などをアンコにしてチヌに割らせる作戦にしました。
ダンゴへの反応は良かったのですが、ダンゴが割れるまで時間がかかるときはチヌは釣れませんでした。
逆にすぐにダンゴが割れる時は、道糸をゆるめてしばらく待っているとチヌが食ってきました。
低水温時はチヌがダンゴに触ってくる回数が少ないので、できるだけ割れやすいダンゴの方が釣果につながると感じました。
また、サシエをダンゴに包まず外に出しておくと、いきなりサシエを食ってくることがありますので、ダンゴには反応があるけれども、なかなかサシエを食って来ないような時は試してみて下さい。
3、サシエサのローテーションは有効か?
紀州釣りではいつもボケをメインに使っています。
ボケに勝るエサはないと思っているので、どんな時でもボケを使って釣行します。
ボケで食わない時は何に変えても食って来ないうえに、オキアミではアタリすらなくエサ取りに取られることが多いので、私の中では「オキアミは使いにくいエサ」という印象があります。
そのような理由から、オキアミやコーンは予備に持って行く程度でメインとしては使いません。
一方、筏釣りでもメインとなるのは何と言ってもボケです。
ところが、同じエサを何度も使っていると魚の反応が悪くなることがあります。
ボケに勝るエサはないはずなのに、チヌが見向きもしなくなるという現象が起こります。
筏では波止と違い、毎日大量にマキエをしている分、お腹がいっぱいで食い渋りという現象が起こるのでは、と考えます。
ボケで反応がない時はオキアミにスイッチしたり、コーンやサナギに変えたりして目先を変えてみると突然食ってくることがあります。
今回はカニやカメジャコといった少し固めのエサに変えると反応が良かったと思います。
食い込みの点ではオキアミでもあまり変わらないと思いますので、オキアミをメインに使ってローテーションしても大丈夫だと思います。
そして、チヌの反応を見るという点でもサシエサはある程度ローテーションした方が釣果につながるのではと感じました。
4、ハワセ釣りは有効か?
紀州釣りではハワセ釣りの方がチヌの食い込みもよく、非常に有効な釣り方です。
ただし、ハワセ釣りは打ち返しのリズムが悪くなるという欠点を併せ持ちますので、チヌを寄せるために大きめのダンゴにするか、追加のダンゴを打つなどの工夫が必要です。
しかし、流れや風のある時に正確にポイントへ追加のダンゴを打つのは困難です。
よく、ウキの上に追加のダンゴを打っている人を見かけますが、ハワセている分、ウキの直下にはサシエはありませんし、ウキが流れる方向とダンゴの濁りが流れる方向が同じでないため、チヌを寄せるどころかチヌを分散させて他人のためにマキエをしているような状態になり逆効果です。
ウキとサシエ、ダンゴの濁りが同じ方向に流れるタナ設定にしないとチヌは釣れませんので、ハワセ幅は最小限で、というのが紀州釣りでは釣りやすいのではないでしょうか。
一方、筏釣りでは竿下を釣りますので、追加のダンゴをどんどん落としてポイントを確立していくことが容易にできます。
ハリスはハワセた方がチヌの食い込みが良いので、ハワセてアタリを待ちます。その後さらに流れた分だけ余分に道糸を送り込むことで、少し離れたところにいるチヌを狙うこともできます。
サシエが流れて行く方向は潮下であり、ダンゴの濁りが流れて行く方向と同じなので、ハワセ幅は無限大で、極端な話、何十メートルハワセても問題ありません。
紀州釣りでも筏のかかり釣りでも、サシエとダンゴの濁りを同調させることは非常に重要で、好釣果を得るための最大のテーマと言えるでしょう。
ちなみに今回の筏かかり釣りのタックルは、
竿:SHIMANO 18セイハコウフィラート160 先調子8:2
リール:SHIMANO セイハコウ60スペシャル RED
道糸、ハリス: VARIBAS筏かかり フロロカーボン2号通し
ハリ:OWNER スーパー競技チヌ3号でした。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。