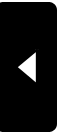紀州釣りでチヌの時合いを考える
釣りには時合いというものがあります。
魚の動きが活発になり、食いが良くなる時間帯の事で、魚が入れ食い状態になったりします。
潮に乗って魚が回遊してきたり、それまで食い気がなくじっとしていた魚が突然食い出したりします。
潮の干満や水温、天候なども関係していると思いますが、実際のところはよくわかりません。

紀州釣りで長年チヌを狙っていますが、この時合いという時間帯がいつ訪れるのか、これといった決まり事はなく、実ははっきりしない事が多いのです。
また、日によっては時合いが全く来ないこともあり、その時は成す術なくボーズになったりします。
魚がよく釣れる時間帯とは一般的に、朝夕のまずめ時と潮止まりの前後です。
ほとんどの釣り人はこれらの時間帯を狙って釣行すると思いますが、紀州釣りではその時間帯に全くチヌが釣れず、予想もしていなかった時間帯に突然チヌが釣れ出すこともあります。
これはチヌとエサ取りとの関係なども大きく影響しているのではと考えています。
エサ取りの活性の高い時間帯では全くチヌが釣れず、エサ取りがいなくなったとたんにチヌが食い出すというのを何度も経験しました。
エサ取りの勢力が強い時は、チヌは周りでこぼれたマキエなどを拾い食いしていることがよくありますが、チヌの数が増えてくると一気にエサ取りを蹴散らしてポイントの中心に入ってきます。
これがチヌの時合いなのですが、チヌの数が少ないと、このようなことが起こりにくく、チヌがたまにポツポツ釣れるといった状態になるわけです。
チヌの時合いをコントロールできるのか?
チヌの時合いを釣り人の思惑どおりコントロールできれば釣果アップは間違いないのですが、そんなことが本当にできるのでしょうか。
釣り人にできる事は、チヌの時合いを予測し、そのための準備をきっちりやっておくということです。
準備というのはマキエのダンゴです。
チヌを寄せるために海底の濁りを絶やさないことは当然ですが、同時に重要なことは、一度寄せたチヌを散らさない工夫も必要だということです。
そのためには、潮流に流されず海底に留まってチヌを足止めさせる効果のあるマキエをダンゴに入れることです。
オキアミやアミエビなど、比重の軽いものはすぐに流されたり、エサ取りに食べられるためマキエの効果が長く持続しません。
押し麦やコーン、アケミ貝やイガイなどは海底に留まりやすいので足止めの効果が長続きします。
また、マキエの仕方についてはある程度のメリハリをつけることも大切です。
昼食前にダンゴを10個ほどドカ撒きしておいて、その後少し場を休めるとチヌが釣れ出したりします。
釣れない時間が長く続くときは、撒く時は撒く、休める時は休める、といった具合にメリハリをつけてポイントに変化をつけてみましょう。
狙うポイントについては基本的には一点集中なのですが、それでも少し広範囲にマキエを効かせておいた方がチヌを寄せやすいので、遠、近、中といった感じにダンゴを打っておき、その中で最も感触の良さそうなポイントを集中的に攻めるようにします。
最後に、知っている人は知っていると思いますが、あまり知られていない時間帯というのがあります。それは午後3時です。
私のよく行く釣り場でも、この時間を境にして急にチヌの活性が上がることが非常に多いです。
かと言って、午後3時から釣行して来る人もたまに見かけますが、その人たちにはほとんどチヌは釣れません。
やはりその時間帯までにダンゴを打っておいて、充分な下準備をしておくことが大切です。
釣れない時間帯も無駄にせず、チヌの時合いを信じてダンゴを打ち続けられる人が、本当の釣り師と言えるのではないでしょうか。
魚の動きが活発になり、食いが良くなる時間帯の事で、魚が入れ食い状態になったりします。
潮に乗って魚が回遊してきたり、それまで食い気がなくじっとしていた魚が突然食い出したりします。
潮の干満や水温、天候なども関係していると思いますが、実際のところはよくわかりません。

紀州釣りで長年チヌを狙っていますが、この時合いという時間帯がいつ訪れるのか、これといった決まり事はなく、実ははっきりしない事が多いのです。
また、日によっては時合いが全く来ないこともあり、その時は成す術なくボーズになったりします。
魚がよく釣れる時間帯とは一般的に、朝夕のまずめ時と潮止まりの前後です。
ほとんどの釣り人はこれらの時間帯を狙って釣行すると思いますが、紀州釣りではその時間帯に全くチヌが釣れず、予想もしていなかった時間帯に突然チヌが釣れ出すこともあります。
これはチヌとエサ取りとの関係なども大きく影響しているのではと考えています。
エサ取りの活性の高い時間帯では全くチヌが釣れず、エサ取りがいなくなったとたんにチヌが食い出すというのを何度も経験しました。
エサ取りの勢力が強い時は、チヌは周りでこぼれたマキエなどを拾い食いしていることがよくありますが、チヌの数が増えてくると一気にエサ取りを蹴散らしてポイントの中心に入ってきます。
これがチヌの時合いなのですが、チヌの数が少ないと、このようなことが起こりにくく、チヌがたまにポツポツ釣れるといった状態になるわけです。
チヌの時合いをコントロールできるのか?
チヌの時合いを釣り人の思惑どおりコントロールできれば釣果アップは間違いないのですが、そんなことが本当にできるのでしょうか。
釣り人にできる事は、チヌの時合いを予測し、そのための準備をきっちりやっておくということです。
準備というのはマキエのダンゴです。
チヌを寄せるために海底の濁りを絶やさないことは当然ですが、同時に重要なことは、一度寄せたチヌを散らさない工夫も必要だということです。
そのためには、潮流に流されず海底に留まってチヌを足止めさせる効果のあるマキエをダンゴに入れることです。
オキアミやアミエビなど、比重の軽いものはすぐに流されたり、エサ取りに食べられるためマキエの効果が長く持続しません。
押し麦やコーン、アケミ貝やイガイなどは海底に留まりやすいので足止めの効果が長続きします。
また、マキエの仕方についてはある程度のメリハリをつけることも大切です。
昼食前にダンゴを10個ほどドカ撒きしておいて、その後少し場を休めるとチヌが釣れ出したりします。
釣れない時間が長く続くときは、撒く時は撒く、休める時は休める、といった具合にメリハリをつけてポイントに変化をつけてみましょう。
狙うポイントについては基本的には一点集中なのですが、それでも少し広範囲にマキエを効かせておいた方がチヌを寄せやすいので、遠、近、中といった感じにダンゴを打っておき、その中で最も感触の良さそうなポイントを集中的に攻めるようにします。
最後に、知っている人は知っていると思いますが、あまり知られていない時間帯というのがあります。それは午後3時です。
私のよく行く釣り場でも、この時間を境にして急にチヌの活性が上がることが非常に多いです。
かと言って、午後3時から釣行して来る人もたまに見かけますが、その人たちにはほとんどチヌは釣れません。
やはりその時間帯までにダンゴを打っておいて、充分な下準備をしておくことが大切です。
釣れない時間帯も無駄にせず、チヌの時合いを信じてダンゴを打ち続けられる人が、本当の釣り師と言えるのではないでしょうか。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。