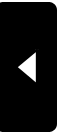紀州釣り-正しい仕掛けの流し方
紀州釣りでチヌを狙う時、正しい仕掛けの流し方があるのをご存じでしょうか?
特に流れのある釣り場では、仕掛けの流し方が間違っていると、チヌはまず釣れません。

■正しい流れを読む
ダンゴが割れれば、あとはチヌが食い付くのを待つだけです。
ところが、いくらチヌがエサを食おうとダンゴの回りに近づいていても、その近くにエサがなければ食うことはできません。
実は、正しい仕掛けの流し方が出来ていないと、ダンゴから飛び出たサシエはあっという間にとんでもない方向に流され、チヌのポイントから外れてしまいます。
こうなってしまうと、せっかく頑張ってチヌを寄せても、多くのチヌを釣る事ができません。
チヌをより確実に釣るためには、チヌが食いやすいように仕掛けを流してやることが大切です。
紀州釣りの場合、サシエは海底付近の流れに乗り、底を這うように流れていくのが普通です。
そしてその流れの先に必ずチヌはいます。
ところが、もし仕掛けが上層の潮に乗ってしまい、その仕掛けに引っ張られ、サシエが底の流れと正反対に流れてしまうとどうなるでしょう。
まずチヌは釣れません。
たとえば、フカセ釣りで最も大切なことは、仕掛けをうまく潮に乗せることです。
しかし、海では普通、複数の潮の流れが存在し、それが釣り人を惑わせます。
重要なのは、乗せるべき潮を正確に読み、正しい流れに仕掛けを乗せることなのです。
仕掛けが乗った潮の先にマキエが効いていなければ、意味がないのです。

■基本はハリス先行
釣りの基本はハリスを先行して流すことです。
道糸が先行してしまうと、仕掛け全体の張りがなくなってアタリが分かりづらいだけでなく、魚の食いそのものが極端に低下します。
ハリスが先行するということは、言い換えればサシエに近い潮、つまり海底付近の潮にうまく乗っているということです。
つまり、ハリスをうまく先行させれば、チヌのポイントをより正確に攻めることができるというわけです。
ハリスを先行させるには、道糸を含めた仕掛け全体の抵抗を少なくしてやる必要があります。
そのためには、ウキや道糸を、海底の流れと逆行する風や、上層の潮などに引っ張られないように工夫しなければなりません。
ダンゴ投入時、ウキや道糸を風上や潮上に持っていくように竿を操作し、仕掛けの抵抗を減らすような工夫が必要です。
また、逆の考え方として、ハリスを太くしてハリスの抵抗を増やし、海底の潮に乗りやすくすることもひとつの方法です。
イメージとしてはハリスを水中ウキのように使うということです。
単純に「ハリスを細くすれば魚が釣れやすい」と思っている人もまだまだ多いようですが、釣り全体についてもっと深く考え、仕掛けや釣り方の工夫をする事で、釣果はもっと伸びるはずです。
特に流れのある釣り場では、仕掛けの流し方が間違っていると、チヌはまず釣れません。

■正しい流れを読む
ダンゴが割れれば、あとはチヌが食い付くのを待つだけです。
ところが、いくらチヌがエサを食おうとダンゴの回りに近づいていても、その近くにエサがなければ食うことはできません。
実は、正しい仕掛けの流し方が出来ていないと、ダンゴから飛び出たサシエはあっという間にとんでもない方向に流され、チヌのポイントから外れてしまいます。
こうなってしまうと、せっかく頑張ってチヌを寄せても、多くのチヌを釣る事ができません。
チヌをより確実に釣るためには、チヌが食いやすいように仕掛けを流してやることが大切です。
紀州釣りの場合、サシエは海底付近の流れに乗り、底を這うように流れていくのが普通です。
そしてその流れの先に必ずチヌはいます。
ところが、もし仕掛けが上層の潮に乗ってしまい、その仕掛けに引っ張られ、サシエが底の流れと正反対に流れてしまうとどうなるでしょう。
まずチヌは釣れません。
たとえば、フカセ釣りで最も大切なことは、仕掛けをうまく潮に乗せることです。
しかし、海では普通、複数の潮の流れが存在し、それが釣り人を惑わせます。
重要なのは、乗せるべき潮を正確に読み、正しい流れに仕掛けを乗せることなのです。
仕掛けが乗った潮の先にマキエが効いていなければ、意味がないのです。

■基本はハリス先行
釣りの基本はハリスを先行して流すことです。
道糸が先行してしまうと、仕掛け全体の張りがなくなってアタリが分かりづらいだけでなく、魚の食いそのものが極端に低下します。
ハリスが先行するということは、言い換えればサシエに近い潮、つまり海底付近の潮にうまく乗っているということです。
つまり、ハリスをうまく先行させれば、チヌのポイントをより正確に攻めることができるというわけです。
ハリスを先行させるには、道糸を含めた仕掛け全体の抵抗を少なくしてやる必要があります。
そのためには、ウキや道糸を、海底の流れと逆行する風や、上層の潮などに引っ張られないように工夫しなければなりません。
ダンゴ投入時、ウキや道糸を風上や潮上に持っていくように竿を操作し、仕掛けの抵抗を減らすような工夫が必要です。
また、逆の考え方として、ハリスを太くしてハリスの抵抗を増やし、海底の潮に乗りやすくすることもひとつの方法です。
イメージとしてはハリスを水中ウキのように使うということです。
単純に「ハリスを細くすれば魚が釣れやすい」と思っている人もまだまだ多いようですが、釣り全体についてもっと深く考え、仕掛けや釣り方の工夫をする事で、釣果はもっと伸びるはずです。
この記事へのコメント
去年から紀州釣りを始めた初心者です!
紀州釣りをしていて、わからないことがたくさんあります。
ダンゴ、タナ、潮や風、遠投など、、、
1つずつクリアしていかないと、釣りにならないんじゃないかと思うようになりました。
何を最初にクリアしていけばいいかアドバイスお願い致します。
紀州釣りをしていて、わからないことがたくさんあります。
ダンゴ、タナ、潮や風、遠投など、、、
1つずつクリアしていかないと、釣りにならないんじゃないかと思うようになりました。
何を最初にクリアしていけばいいかアドバイスお願い致します。
くろだぃさん、コメントありがとうございます。
ブログ管理人です。
去年から紀州釣りを始めた初心者とのことですが、最初はわからないことだらけですね。
何を最初にクリアしていけばいいかというご質問ですが、
まずはダンゴとタナの調整。これを同時にやってみて下さい。
潮や風、遠投は難しいので後からでもいいです。
テーマは
1、ダンゴは必ず海底まで届くこと。
2、ウキ下は底トントンから始めること。
実釣をイメージしてシミュレーションしてみます。
修行場所として、潮の緩い波止などの釣り場へ釣行します。
投点は捨石の少し向こう10m~15mくらいの平坦な砂底を狙います。水深3ヒロ半。
ダンゴは少しパサパサ目でしっとりした感じ。片手で握っても何とか形になるぐらい。
直径6cmぐらいのダンゴを両手で握り、背丈から落としても割れないぐらいの硬さにします。
ダンゴは中層で魚が突いて来ますが、絶対に途中で割れたらダメです。
その時点でタナが分からなくなるからです。
ダンゴを投げたらウキが付いていきます。ウキは寝ウキ15cmを使用。
ウキは一旦沈んですぐに浮いてきますが、ダンゴの重みを感じ、少しシモった感じになり、寝ウキが立っています。
これが底トントンのタナです。
シモった感じがなければハワセ気味かハワセ過ぎ。
ウキが浮いてこなければタナが足りません。
ウキがシモった状態から解放され、ダンゴのテンションがかからず自由な感じになったらダンゴが割れた証拠です。
この時、タナが合っていないとダンゴが割れた瞬間が分かりません。
ダンゴが割れた瞬間が分かるタナになるように何度も何度も調整してください。
このタナ取りの調整がきちんとできることが紀州釣りの第一歩です。
また、タナ調整の良し悪しが釣果を大きく左右します。
注意点として、ダンゴがあまりにも早く割れてしまうとタナが合ってるか合っていないかが分からないので、仕掛けが潮に馴染むまでダンゴが割れないように硬さを調整します。
ただし、この一連の動きは潮や風に邪魔されると非常にに分かりづらくなります。
ダンゴとタナに関しては、色んな状況で多くの経験を積むことが大切です。
まずは自分のスタイルを確立し、信じて続けることです。
ブログ管理人です。
去年から紀州釣りを始めた初心者とのことですが、最初はわからないことだらけですね。
何を最初にクリアしていけばいいかというご質問ですが、
まずはダンゴとタナの調整。これを同時にやってみて下さい。
潮や風、遠投は難しいので後からでもいいです。
テーマは
1、ダンゴは必ず海底まで届くこと。
2、ウキ下は底トントンから始めること。
実釣をイメージしてシミュレーションしてみます。
修行場所として、潮の緩い波止などの釣り場へ釣行します。
投点は捨石の少し向こう10m~15mくらいの平坦な砂底を狙います。水深3ヒロ半。
ダンゴは少しパサパサ目でしっとりした感じ。片手で握っても何とか形になるぐらい。
直径6cmぐらいのダンゴを両手で握り、背丈から落としても割れないぐらいの硬さにします。
ダンゴは中層で魚が突いて来ますが、絶対に途中で割れたらダメです。
その時点でタナが分からなくなるからです。
ダンゴを投げたらウキが付いていきます。ウキは寝ウキ15cmを使用。
ウキは一旦沈んですぐに浮いてきますが、ダンゴの重みを感じ、少しシモった感じになり、寝ウキが立っています。
これが底トントンのタナです。
シモった感じがなければハワセ気味かハワセ過ぎ。
ウキが浮いてこなければタナが足りません。
ウキがシモった状態から解放され、ダンゴのテンションがかからず自由な感じになったらダンゴが割れた証拠です。
この時、タナが合っていないとダンゴが割れた瞬間が分かりません。
ダンゴが割れた瞬間が分かるタナになるように何度も何度も調整してください。
このタナ取りの調整がきちんとできることが紀州釣りの第一歩です。
また、タナ調整の良し悪しが釣果を大きく左右します。
注意点として、ダンゴがあまりにも早く割れてしまうとタナが合ってるか合っていないかが分からないので、仕掛けが潮に馴染むまでダンゴが割れないように硬さを調整します。
ただし、この一連の動きは潮や風に邪魔されると非常にに分かりづらくなります。
ダンゴとタナに関しては、色んな状況で多くの経験を積むことが大切です。
まずは自分のスタイルを確立し、信じて続けることです。
コメントありがとうございます!
ダンゴを固めにして、タナはトントンでダンゴ割れがわかるようにすればいいとのことですね!
助言ありがとうございます!
あと無理に遠投する必要はないですか?周りで紀州釣りされている人がいると遠くへ飛ばさないと寄りが悪いかなーとおもってしまうのですが、、、どうでしょうか?
ダンゴを固めにして、タナはトントンでダンゴ割れがわかるようにすればいいとのことですね!
助言ありがとうございます!
あと無理に遠投する必要はないですか?周りで紀州釣りされている人がいると遠くへ飛ばさないと寄りが悪いかなーとおもってしまうのですが、、、どうでしょうか?
くろだぃさん、コメントありがとうございます。
ダンゴの遠投について
チヌの寄りに関して言うと、遠投でも手前でもあまり関係がないです。
いかに同じところにダンゴを入れ続けるかが最も重要だからです。
他の紀州釣りの人がいてもいなくてもそれは同じことです。
ただし沖にシモリなど、チヌの通り道となるようなポイントがあり、手前より条件が良いなどの場合は別ですが。
また、寄せやすさと釣りやすさで言えば、圧倒的に手前が有利です。
手前はダンゴ投入点があまりずれませんのでポイントを作りやすいです。
そして潮や風の影響も遠投に比べて極端に少ないので、タナが狂いにくくなります。
また、手前はエサ取りが多いのでダンゴの割れが早くなります。
ダンゴの割れが確認できるタナにしておくことで、自然と手返しも早くなります。
手返しが早くなればダンゴの煙幕効果が大きくなり、チヌの寄りが良くなります。
ただ、手前は先ほども言ったようにエサ取りが多いです。
チヌの数が少ない時は、エサ取りを避けるため少しづつ沖にポイントを移動していくような釣り方も時には必要です。
無理に遠投する必要は全くないですが、遠投しないと釣れない場合もあるので
遠投の技術は磨いておく必要があります。
上手に遠投出来れば見た目もかっこいいし、釣りの幅も広がりますよね。
上手に投げれるようになれば、距離を競い合うのも面白いです。
私も普段は90センチくらいの杓で30~40mほど遠投します。
人より遠くに投げることは快感ですが、チヌが釣れないと意味がないです。
遠投でチヌを釣る場合は、コントロールと手返しが重要になります。
見た目かっこよく遠投している人でも、
コントロールが悪かったり手返しが遅い人を見ると、
「あぁこの人は今日、チヌが釣れないだろうな」と思ってしまいます。
杓を使って上手に遠投する場合の注意点ですが、私の経験から言うと何と言ってもグリップです。
杓のグリップが手に合っていないと変に力が入って方向や距離が定まりません。
自分の手の大きさや握りに合った、自分専用の握りやすいグリップが必要です。
重要なのは、握った時、カップがいつも同じ方向を向いていることです。
紀州釣りは遠投することによって、より面白さが増します。
その半面、難しさが倍増してきますので、ここからは修行あるのみ!って感じです。
遠投を征するには、潮と風と杓を征することです。
遠投の技術を磨くには近道はありません。回数を重ね、経験を積むことです。
ダンゴの遠投について
チヌの寄りに関して言うと、遠投でも手前でもあまり関係がないです。
いかに同じところにダンゴを入れ続けるかが最も重要だからです。
他の紀州釣りの人がいてもいなくてもそれは同じことです。
ただし沖にシモリなど、チヌの通り道となるようなポイントがあり、手前より条件が良いなどの場合は別ですが。
また、寄せやすさと釣りやすさで言えば、圧倒的に手前が有利です。
手前はダンゴ投入点があまりずれませんのでポイントを作りやすいです。
そして潮や風の影響も遠投に比べて極端に少ないので、タナが狂いにくくなります。
また、手前はエサ取りが多いのでダンゴの割れが早くなります。
ダンゴの割れが確認できるタナにしておくことで、自然と手返しも早くなります。
手返しが早くなればダンゴの煙幕効果が大きくなり、チヌの寄りが良くなります。
ただ、手前は先ほども言ったようにエサ取りが多いです。
チヌの数が少ない時は、エサ取りを避けるため少しづつ沖にポイントを移動していくような釣り方も時には必要です。
無理に遠投する必要は全くないですが、遠投しないと釣れない場合もあるので
遠投の技術は磨いておく必要があります。
上手に遠投出来れば見た目もかっこいいし、釣りの幅も広がりますよね。
上手に投げれるようになれば、距離を競い合うのも面白いです。
私も普段は90センチくらいの杓で30~40mほど遠投します。
人より遠くに投げることは快感ですが、チヌが釣れないと意味がないです。
遠投でチヌを釣る場合は、コントロールと手返しが重要になります。
見た目かっこよく遠投している人でも、
コントロールが悪かったり手返しが遅い人を見ると、
「あぁこの人は今日、チヌが釣れないだろうな」と思ってしまいます。
杓を使って上手に遠投する場合の注意点ですが、私の経験から言うと何と言ってもグリップです。
杓のグリップが手に合っていないと変に力が入って方向や距離が定まりません。
自分の手の大きさや握りに合った、自分専用の握りやすいグリップが必要です。
重要なのは、握った時、カップがいつも同じ方向を向いていることです。
紀州釣りは遠投することによって、より面白さが増します。
その半面、難しさが倍増してきますので、ここからは修行あるのみ!って感じです。
遠投を征するには、潮と風と杓を征することです。
遠投の技術を磨くには近道はありません。回数を重ね、経験を積むことです。
参考になりました!
ありがとうございます。
いま22歳なので、いまからいっぱい練習して紀州釣りを極めれるように頑張ります!
またわからない事があれば、コメントさせてもらいます!
どのサイトよりも紀州釣りの事がわかりやすいので、投稿やめないでくださいね(笑)
ありがとうございます。
いま22歳なので、いまからいっぱい練習して紀州釣りを極めれるように頑張ります!
またわからない事があれば、コメントさせてもらいます!
どのサイトよりも紀州釣りの事がわかりやすいので、投稿やめないでくださいね(笑)
こんにちは。紀州釣りを始めて3ヶ月ですが、釣行は4回しか行けてません。いつもブログを読ませて頂きイメージしながら勉強中です。2.3点教えて頂きたい事があります。1.ハワセ釣りの場合、海底にダンゴが着底しウキが水面に上がってきますが(寝ウキ使用)ダンゴの重みがウキに伝わらない為ウキがずっと寝ている状態になります。ダンゴが割れた瞬間がわかりません。どのようにしたら良いでしょうか。底トントンでウキの先端近くが見えておりダンゴが割れるとポンッと浮いてくることまでは出来るようになりました。宜しくお願します。
チヌつりたい さん、コメントありがとうございます。
ハワセ釣りに関する質問ですね。
答えが長くなりますがしっかり読んで理解して下さい。
まず、なぜハワセ釣りをするのか?
その理由によって答えは変わってくると思います。
1、チヌの食いを優先させるためにハワセ釣りをする場合
この場合のハワセ釣りでは、ダンゴが割れた瞬間が分からないようなタナに設定します。
ダンゴが割れた瞬間が分かるという事は、
ハリスに何らかのテンションがかかっているわけですので、
チヌの食いを優先させるためにハワセ釣りをするなら、
ダンゴが割れた瞬間が分からないようなウキ下にしないと全く意味がありません。
この時、ハリスの一部または全体を海底にハワセてアタリを待ちます。
アタリはチヌが食って移動したときにしか出ません。
どうしてもダンゴが割れた瞬間を知りたい場合は、道糸を少し張った状態で寝ウキにテンションをかけて立たせておいて、ダンゴが割れるのを待ちます。
ダンゴが割れたら、ウキが寝ますので、すぐに道糸をゆるめて潮に馴染ませます。
この方法は、筏のかかり釣りでもよく用いますが、ダンゴが割れてからハリスが海底に馴染むまで少し流されますので、場合によってはサシエも若干移動します。
サシエを移動させたくない場合はテンションをかけずにダンゴが割れるのを待つしかありません。
2、潮流や風の影響で仕掛けが舞い上がるのを防止するためにハワセる場合
このケースが実釣では最も多いと思います。
このような場合も「ハワセ釣り」ですが、実際にハリスが海底に這っていなくても「ハワセ釣り」と言います。
この場合のハワセというのは、潮の流れなどで仕掛けが斜めになるため、
その分水深よりもタナを深く設定してウキが沈むのを防止するのが目的なので、
実際にハリスが底に這っている必要はありません。
もちろんハリスが底に這っている場合もありますが、サシエが底にあればそれで良いです。
仕掛けが斜めになった状態でもウキにダンゴの重みが伝わり、ウキが少し反応している状態のタナに設定すれば、ダンゴが割れた瞬間が分かるようになります。
たとえば一番高い波の位置でウキが少しシモるようにタナを設定し、高い波でシモらないようになればダンゴが割れたということです。
寝ウキが波で立ったり寝たりを繰り返しますが、そのリズムが崩れた瞬間がダンゴが割れた合図になります。
また、流れのある釣り場では、ダンゴが割れるまではウキは止まったままですが、
ダンゴが割れると潮に流され移動しますので、これがダンゴが割れた合図になります。
基本、釣り始めは底トントンのタナで釣りをして、ダンゴが割れるタイミングを確認します。
そうすると、どれくらいの時間でダンゴが割れるか分かるようになりますので、それからハワセに移行するのが良いと思います。
3、エサ取りをかわすためにハワセ釣りをする場合
どれくらいハワセてエサ取りをかわすかによって変わってきますが、
この場合は最初の方法と後の方法の中間の考え方で良いと思います。
だいたい以上の事を参考にして、これからも紀州釣りを楽しんで下さい。
ハワセ釣りに関する質問ですね。
答えが長くなりますがしっかり読んで理解して下さい。
まず、なぜハワセ釣りをするのか?
その理由によって答えは変わってくると思います。
1、チヌの食いを優先させるためにハワセ釣りをする場合
この場合のハワセ釣りでは、ダンゴが割れた瞬間が分からないようなタナに設定します。
ダンゴが割れた瞬間が分かるという事は、
ハリスに何らかのテンションがかかっているわけですので、
チヌの食いを優先させるためにハワセ釣りをするなら、
ダンゴが割れた瞬間が分からないようなウキ下にしないと全く意味がありません。
この時、ハリスの一部または全体を海底にハワセてアタリを待ちます。
アタリはチヌが食って移動したときにしか出ません。
どうしてもダンゴが割れた瞬間を知りたい場合は、道糸を少し張った状態で寝ウキにテンションをかけて立たせておいて、ダンゴが割れるのを待ちます。
ダンゴが割れたら、ウキが寝ますので、すぐに道糸をゆるめて潮に馴染ませます。
この方法は、筏のかかり釣りでもよく用いますが、ダンゴが割れてからハリスが海底に馴染むまで少し流されますので、場合によってはサシエも若干移動します。
サシエを移動させたくない場合はテンションをかけずにダンゴが割れるのを待つしかありません。
2、潮流や風の影響で仕掛けが舞い上がるのを防止するためにハワセる場合
このケースが実釣では最も多いと思います。
このような場合も「ハワセ釣り」ですが、実際にハリスが海底に這っていなくても「ハワセ釣り」と言います。
この場合のハワセというのは、潮の流れなどで仕掛けが斜めになるため、
その分水深よりもタナを深く設定してウキが沈むのを防止するのが目的なので、
実際にハリスが底に這っている必要はありません。
もちろんハリスが底に這っている場合もありますが、サシエが底にあればそれで良いです。
仕掛けが斜めになった状態でもウキにダンゴの重みが伝わり、ウキが少し反応している状態のタナに設定すれば、ダンゴが割れた瞬間が分かるようになります。
たとえば一番高い波の位置でウキが少しシモるようにタナを設定し、高い波でシモらないようになればダンゴが割れたということです。
寝ウキが波で立ったり寝たりを繰り返しますが、そのリズムが崩れた瞬間がダンゴが割れた合図になります。
また、流れのある釣り場では、ダンゴが割れるまではウキは止まったままですが、
ダンゴが割れると潮に流され移動しますので、これがダンゴが割れた合図になります。
基本、釣り始めは底トントンのタナで釣りをして、ダンゴが割れるタイミングを確認します。
そうすると、どれくらいの時間でダンゴが割れるか分かるようになりますので、それからハワセに移行するのが良いと思います。
3、エサ取りをかわすためにハワセ釣りをする場合
どれくらいハワセてエサ取りをかわすかによって変わってきますが、
この場合は最初の方法と後の方法の中間の考え方で良いと思います。
だいたい以上の事を参考にして、これからも紀州釣りを楽しんで下さい。
なるほど!なるほど!なるほど!と思うぐらいのご丁寧な回答ありがとうございました。ハワセ釣りでこれだけの内容があるのですね。
非常に参考になりました。不明な点が解消されスッとしております。次回の釣行で実践してみたいと思います。ありがとうございました。1匹釣れたらUPさせて頂きます。
非常に参考になりました。不明な点が解消されスッとしております。次回の釣行で実践してみたいと思います。ありがとうございました。1匹釣れたらUPさせて頂きます。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。