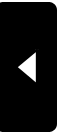紀州釣りでチヌが釣れない理由
紀州釣りをやっていて、なぜか思うように釣れない。
他の釣り人に比べ、どうしても釣果が伸びない。
どんなに頑張っても、釣れるのはエサ取りやボラばかり・・・
そういう時、釣れない原因は必ずあります。
自分の釣り方のどこにその原因があるのか、ちょっと考えてみましょう。

■チヌが寄っていない
まず、第一に考えなければならないのが、ちゃんとチヌが寄っているのか?ということです。
紀州釣りは、ダンゴの投入によってチヌを自分のポイントまで寄せて釣ります。
ここで大切なのがダンゴの投入数です。
チヌはダンゴの投入数に比例して、釣れる数も変わってきます。
よりたくさんのダンゴを打つことで、より多くのチヌが集まるのです。
ここで間違えやすいのは「ダンゴの量」ではなく、「ダンゴの数」ということです。
これは打ち返しの数やリズムとも関係することなので、ただ単にマキエの量が多いか少ないかではなく、その「回数」が重要になってきます。
少ない量でも、絶え間なくマキエを打ち続けることが何より重要です。
そしてもうひとつ、ダンゴの「着底点」がどれだけ正確か?ということも大事です。
同じところに投げているつもりでも、ダンゴは潮流によって流されています。
ダンゴが海底に着いたときバラバラの位置では意味がないのです。
潮流を読みながら、正確な場所に投入しなければ多くのチヌを釣り上げることはできません。
また、ダンゴが沈んでいく途中でバラケてしまうようなダンゴは問題外として、表層から中層にかけて濁りの帯が出てしまうようなダンゴも、海底で効果的にチヌを集めるには不向きです。
海底に到達してからバラケが始まるダンゴが、紀州釣りでは理想的なダンゴなのです。
■アワセのタイミング
せっかくチヌを寄せても、アワセのタイミングがずれているとチヌは釣れません。
絶対に釣れないパターンとして例にあげると、チヌがエサを食う前にアワセを入れている人が結構います。
初心者では大半の人が、中級者の人でも半分ぐらいの人が、また、上級者っぽい方でもたまに犯してしまうアワセのミス(空振り)がこれです。
私はこれを「ダンゴ合わせ」と言っています。
つまり、ダンゴがまだ割れていない状態で、ダンゴの重みでウキがシモっているのを見極められず、魚のアタリと勘違いしてアワセを入れてしまうケースです。
「そんな人いないだろ!」
と思ったあなたは、まぎれもなく初心者です。
自分のミスに気づかないだけで、知らず知らずのうちに「ダンゴアワセ」をしてしまっているのかもしれませんよ。
たとえば、ボラをたくさん釣る人は、必ずといっていいほど「ダンゴアワセ」をしています。
ボラのスレアタリが出ている時や、ボラがスレで掛かるときもまだダンゴが割れていない状態なので、ここでもアタリの見極めができていないと、ボラばかり釣れることになります。
特に、潮流の早いときや、風の強いとき、ダンゴの割れが遅いときなど、「いつダンゴが割れたのか?」を正確に、そして確実に把握するのは、かなり難しいものです。
「ウキにテンションがかかっていないから」
「ウキが浮いてきたから」
それだけの理由でダンゴが割れたと思うのは間違いで、それは道糸に張りができていないためウキがダンゴの重みを伝えきれていないだけかもしれないのです。
また、ダンゴは割れても最後に「芯」が残ることがあります。
こんなときも、ウキには「割れたような合図」が出ますがダンゴの残骸が残っているこの一瞬こそ最もボラが食いつきやすい状態でもあります。
これらをきっちりと見極められるようになるには、やはりある程度の経験が必要なのかもしれませんが、少しづつ慣れればいいと思います。
■サシエがポイントから外れる
ダンゴが割れれば、あとは自然にサシエを流してチヌのアタリを待ちます。
ただしこの時、サシエがチヌのポイントから外れると全く釣れません。
にもかかわらず、チヌのポイントから完全に外れていることに気付かず、いつまでも仕掛けを流している人がいます。とても効率の悪い釣り方です。
サシエがチヌのポイントから外れる最大の原因は、道糸が潮流や風で流され、仕掛け全体を引っ張ってしまうことにあります。
ダンゴが割れるまでにはある程度の時間が必要ですが、その間道糸は、潮流や風によって知らず知らずにどんどん流されています。
このとき、道糸を含め仕掛け全体には強い張りができていて、ダンゴが割れると同時にサシエを大きく浮き上がらせながら、素早くポイントから離れていきます。
このような状態では、海底でエサを待っているチヌはおろか、ダンゴにアタックしている食い気満々のチヌでさえ、サシエを食うことが困難になります。
また、どんどん遠ざかっていくサシエを追いかけてまで食ってくるチヌなど、ほとんどいません。
いるとすれば、濁りの外側でうろついている活性の低いチヌぐらいですが、その前に立ちはだかる無数のエサ取りの層を突破しなければなりませんし、それ以上に、活性の低いチヌにサシエを食わせるのはとても難しいことなのです。
このように、ダンゴが割れて、飛び出したサシエが、できるだけそのままの位置で安定していることがチヌを釣るためのひとつの条件です。
サシエを安定させるには、ダンゴの投入と同時に道糸を操作し、ウキを風上や潮上に持って行くことが必要になります。
また、同様に道糸を風上や潮上に持って行く操作をダンゴが割れるまでの間、何度も繰り返し行います。
この操作を行うのと行わないのとでは、釣果に天と地の差が出ますので、必ずマスターしておいてください。
ただし、この道糸操作はウキにあまりテンションが掛からない範囲で行います。
無理に引っ張るとダンゴごと仕掛けが移動してしまうなど、逆効果になることもありますので、出来れば道糸を操作しやすいフロートラインを使うと良いでしょう。
このように、サシエがポイントから流されないための工夫がどうしても必要ですが、ダンゴの投入点の少しの違いによっても、仕掛け全体の流される方向が変わることがよくありますので、投入点は正確に覚えておかなければなりません。
また、左右どちらに流れたときにアタリが多いかなど、状況を見ながらチヌの居場所を推理し、攻略することも大切です。
■タナが合っていない
紀州釣りでは、水深よりも深めにタナを設定するわけですが、それがきちんと出来ていないとチヌは釣れません。
ダンゴに寄ったチヌは主に海底のエサを食べる習性があります。 なので、サシエが海底から少しでも浮き上がると、極端に食いが悪くなります。
紀州釣りに限らず、海釣りでは流れがあるため、仕掛けは必ず斜めになります。
斜めの角度は、「潮流の速さ」と「風の強さ」、それに「水深」さらには「ウキの浮力」が関係してきます。
紀州釣りでタナを決めるときは、水深ではなく、この斜めの距離に合わせることが重要です。
この距離を考えず、水深だけを見て適当にタナを決めてしまうと、サシエは簡単に浮き上がってしまいます。
ただ、エサが浮き上がっているかいないのか、慣れるまでは判断が少し難しいかもしれません。
ですが、たとえばエサ取りが掛かったとき、ハリの掛かった位置が上あごなら、それは完全にエサが浮いている証拠です。
こんなときはすぐに修正して、適切なタナに合わせ直しましょう。
他の釣り人に比べ、どうしても釣果が伸びない。
どんなに頑張っても、釣れるのはエサ取りやボラばかり・・・
そういう時、釣れない原因は必ずあります。
自分の釣り方のどこにその原因があるのか、ちょっと考えてみましょう。

■チヌが寄っていない
まず、第一に考えなければならないのが、ちゃんとチヌが寄っているのか?ということです。
紀州釣りは、ダンゴの投入によってチヌを自分のポイントまで寄せて釣ります。
ここで大切なのがダンゴの投入数です。
チヌはダンゴの投入数に比例して、釣れる数も変わってきます。
よりたくさんのダンゴを打つことで、より多くのチヌが集まるのです。
ここで間違えやすいのは「ダンゴの量」ではなく、「ダンゴの数」ということです。
これは打ち返しの数やリズムとも関係することなので、ただ単にマキエの量が多いか少ないかではなく、その「回数」が重要になってきます。
少ない量でも、絶え間なくマキエを打ち続けることが何より重要です。
そしてもうひとつ、ダンゴの「着底点」がどれだけ正確か?ということも大事です。
同じところに投げているつもりでも、ダンゴは潮流によって流されています。
ダンゴが海底に着いたときバラバラの位置では意味がないのです。
潮流を読みながら、正確な場所に投入しなければ多くのチヌを釣り上げることはできません。
また、ダンゴが沈んでいく途中でバラケてしまうようなダンゴは問題外として、表層から中層にかけて濁りの帯が出てしまうようなダンゴも、海底で効果的にチヌを集めるには不向きです。
海底に到達してからバラケが始まるダンゴが、紀州釣りでは理想的なダンゴなのです。
■アワセのタイミング
せっかくチヌを寄せても、アワセのタイミングがずれているとチヌは釣れません。
絶対に釣れないパターンとして例にあげると、チヌがエサを食う前にアワセを入れている人が結構います。
初心者では大半の人が、中級者の人でも半分ぐらいの人が、また、上級者っぽい方でもたまに犯してしまうアワセのミス(空振り)がこれです。
私はこれを「ダンゴ合わせ」と言っています。
つまり、ダンゴがまだ割れていない状態で、ダンゴの重みでウキがシモっているのを見極められず、魚のアタリと勘違いしてアワセを入れてしまうケースです。
「そんな人いないだろ!」
と思ったあなたは、まぎれもなく初心者です。
自分のミスに気づかないだけで、知らず知らずのうちに「ダンゴアワセ」をしてしまっているのかもしれませんよ。
たとえば、ボラをたくさん釣る人は、必ずといっていいほど「ダンゴアワセ」をしています。
ボラのスレアタリが出ている時や、ボラがスレで掛かるときもまだダンゴが割れていない状態なので、ここでもアタリの見極めができていないと、ボラばかり釣れることになります。
特に、潮流の早いときや、風の強いとき、ダンゴの割れが遅いときなど、「いつダンゴが割れたのか?」を正確に、そして確実に把握するのは、かなり難しいものです。
「ウキにテンションがかかっていないから」
「ウキが浮いてきたから」
それだけの理由でダンゴが割れたと思うのは間違いで、それは道糸に張りができていないためウキがダンゴの重みを伝えきれていないだけかもしれないのです。
また、ダンゴは割れても最後に「芯」が残ることがあります。
こんなときも、ウキには「割れたような合図」が出ますがダンゴの残骸が残っているこの一瞬こそ最もボラが食いつきやすい状態でもあります。
これらをきっちりと見極められるようになるには、やはりある程度の経験が必要なのかもしれませんが、少しづつ慣れればいいと思います。
■サシエがポイントから外れる
ダンゴが割れれば、あとは自然にサシエを流してチヌのアタリを待ちます。
ただしこの時、サシエがチヌのポイントから外れると全く釣れません。
にもかかわらず、チヌのポイントから完全に外れていることに気付かず、いつまでも仕掛けを流している人がいます。とても効率の悪い釣り方です。
サシエがチヌのポイントから外れる最大の原因は、道糸が潮流や風で流され、仕掛け全体を引っ張ってしまうことにあります。
ダンゴが割れるまでにはある程度の時間が必要ですが、その間道糸は、潮流や風によって知らず知らずにどんどん流されています。
このとき、道糸を含め仕掛け全体には強い張りができていて、ダンゴが割れると同時にサシエを大きく浮き上がらせながら、素早くポイントから離れていきます。
このような状態では、海底でエサを待っているチヌはおろか、ダンゴにアタックしている食い気満々のチヌでさえ、サシエを食うことが困難になります。
また、どんどん遠ざかっていくサシエを追いかけてまで食ってくるチヌなど、ほとんどいません。
いるとすれば、濁りの外側でうろついている活性の低いチヌぐらいですが、その前に立ちはだかる無数のエサ取りの層を突破しなければなりませんし、それ以上に、活性の低いチヌにサシエを食わせるのはとても難しいことなのです。
このように、ダンゴが割れて、飛び出したサシエが、できるだけそのままの位置で安定していることがチヌを釣るためのひとつの条件です。
サシエを安定させるには、ダンゴの投入と同時に道糸を操作し、ウキを風上や潮上に持って行くことが必要になります。
また、同様に道糸を風上や潮上に持って行く操作をダンゴが割れるまでの間、何度も繰り返し行います。
この操作を行うのと行わないのとでは、釣果に天と地の差が出ますので、必ずマスターしておいてください。
ただし、この道糸操作はウキにあまりテンションが掛からない範囲で行います。
無理に引っ張るとダンゴごと仕掛けが移動してしまうなど、逆効果になることもありますので、出来れば道糸を操作しやすいフロートラインを使うと良いでしょう。
このように、サシエがポイントから流されないための工夫がどうしても必要ですが、ダンゴの投入点の少しの違いによっても、仕掛け全体の流される方向が変わることがよくありますので、投入点は正確に覚えておかなければなりません。
また、左右どちらに流れたときにアタリが多いかなど、状況を見ながらチヌの居場所を推理し、攻略することも大切です。
■タナが合っていない
紀州釣りでは、水深よりも深めにタナを設定するわけですが、それがきちんと出来ていないとチヌは釣れません。
ダンゴに寄ったチヌは主に海底のエサを食べる習性があります。 なので、サシエが海底から少しでも浮き上がると、極端に食いが悪くなります。
紀州釣りに限らず、海釣りでは流れがあるため、仕掛けは必ず斜めになります。
斜めの角度は、「潮流の速さ」と「風の強さ」、それに「水深」さらには「ウキの浮力」が関係してきます。
紀州釣りでタナを決めるときは、水深ではなく、この斜めの距離に合わせることが重要です。
この距離を考えず、水深だけを見て適当にタナを決めてしまうと、サシエは簡単に浮き上がってしまいます。
ただ、エサが浮き上がっているかいないのか、慣れるまでは判断が少し難しいかもしれません。
ですが、たとえばエサ取りが掛かったとき、ハリの掛かった位置が上あごなら、それは完全にエサが浮いている証拠です。
こんなときはすぐに修正して、適切なタナに合わせ直しましょう。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。