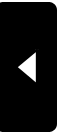紀州釣りの玉ウキと寝ウキ
紀州釣りのウキは、一般的に10~20cmくらいの寝ウキ、直径1~2cmくらいの玉ウキを使います。
素材は発泡製や木製になりますが、紀州釣りで使用するウキの場合、「潮流に負けない浮力」と、「感度の良さ」が重要になります。
棒ウキは、よほどの好条件に恵まれない限り使用することは少ないでしょう。
紀州釣りではダンゴを使うため、その重さに対してある程度踏ん張りの効くウキが必要になります。
かと言って、魚のアタリに反応が出ないような感度の悪いウキでは話になりません。
浮力があって感度が良い。この2つを合わせ持つのが発泡製や木製の玉ウキと寝ウキなのです。
それでは具体的に玉ウキと寝ウキについてお話しましょう。
まず、玉ウキの長所としては、小さくても浮力があるため、潮流に負けず、常に海面を漂わせることが容易にでき、エサの浮き上りを防げます。
潮流が速い場所や水深のある釣り場では、その威力を発揮します。
また、釣り座が高い場合は、視認性に優れているのも特徴です。
上から海面を見るような状況では、玉ウキのように表面積が大きい方が見やすくなります。
ベタ凪に近い状態で使用すると、小さいアタリに対して水面に波紋が出来るので見ていて楽しいです。
荒波の時は、ウキの上下動のリズムが崩れた時がアタリです。
玉ウキの場合、最初は小さいアタリが分かりづらいと感じるかも知れませんが、ある程度慣れれば解消できます。
次に、寝ウキの長所ですが、これは玉ウキの欠点である『風』に対して非常に強いと言う点です。
強風で玉ウキがどんどん風下へ流され、ウキが仕掛けを大きく引っ張ってしまって全く釣りにならない時があります。
しかし寝ウキの場合は水面からの露出が少なく、しかも風に対して水平に向きを変えるため、風を受ける面積が非常に小さくなります。
その結果、強風下でも仕掛けがポイントから外れずに安定した釣果が期待できます。
過去に強風時、玉ウキ8、寝ウキ2の割合で使った時の話ですが、その時は釣果の全てが寝ウキでした。
寝ウキはアタリも明確で、小さなアタリも取りやすいのが特徴です。
アタリを見る楽しさから言うとこちらがオススメです。
ただし、水深のある釣り場で流れが極端に速い場合は、ダンゴが割れるまでにウキが海中に沈んでしまうという欠点もあります。
この場合はかなり浮力の大きい寝ウキを使う必要がありますので、小さいアタリは解りにくくなります。
お互いの欠点をカバーしつつ、浮力があり感度のよい寝ウキの最終形としては、とうがらし型の寝ウキということになります。

上の写真の寝ウキですが、根元の方が太く、先端に向かってだんだん細くなるようにテーパーを付けています。
これは普通の寝ウキに比べ、浮力があって感度が良い形状です。エサ取りの小さいアタリでも反応が良いです。
このタイプのウキはあまり市販されていないので、時間があれば自作してみてはいかがでしょう。
下の写真は直径8mmのバルサ材や桐材で作っています。11~17cmです。

市販で近いものと言えば、大西ウキというのもこのような形状をしていて人気があります。
下の写真の上3つが大西ウキです。

ウキの色は、私の経験では蛍光のオレンジが最も見やすく、次に蛍光の赤、蛍光の黄色、蛍光の緑となります。
ただし状況によっては順番が前後する場合もあります。
また、夕日が眩しい場合は黒いウキを使うと見やすくなりますので、ひとつ持っておくと便利でしょう。
素材は発泡製や木製になりますが、紀州釣りで使用するウキの場合、「潮流に負けない浮力」と、「感度の良さ」が重要になります。
棒ウキは、よほどの好条件に恵まれない限り使用することは少ないでしょう。
紀州釣りではダンゴを使うため、その重さに対してある程度踏ん張りの効くウキが必要になります。
かと言って、魚のアタリに反応が出ないような感度の悪いウキでは話になりません。
浮力があって感度が良い。この2つを合わせ持つのが発泡製や木製の玉ウキと寝ウキなのです。
それでは具体的に玉ウキと寝ウキについてお話しましょう。
まず、玉ウキの長所としては、小さくても浮力があるため、潮流に負けず、常に海面を漂わせることが容易にでき、エサの浮き上りを防げます。
潮流が速い場所や水深のある釣り場では、その威力を発揮します。
また、釣り座が高い場合は、視認性に優れているのも特徴です。
上から海面を見るような状況では、玉ウキのように表面積が大きい方が見やすくなります。
ベタ凪に近い状態で使用すると、小さいアタリに対して水面に波紋が出来るので見ていて楽しいです。
荒波の時は、ウキの上下動のリズムが崩れた時がアタリです。
玉ウキの場合、最初は小さいアタリが分かりづらいと感じるかも知れませんが、ある程度慣れれば解消できます。
次に、寝ウキの長所ですが、これは玉ウキの欠点である『風』に対して非常に強いと言う点です。
強風で玉ウキがどんどん風下へ流され、ウキが仕掛けを大きく引っ張ってしまって全く釣りにならない時があります。
しかし寝ウキの場合は水面からの露出が少なく、しかも風に対して水平に向きを変えるため、風を受ける面積が非常に小さくなります。
その結果、強風下でも仕掛けがポイントから外れずに安定した釣果が期待できます。
過去に強風時、玉ウキ8、寝ウキ2の割合で使った時の話ですが、その時は釣果の全てが寝ウキでした。
寝ウキはアタリも明確で、小さなアタリも取りやすいのが特徴です。
アタリを見る楽しさから言うとこちらがオススメです。
ただし、水深のある釣り場で流れが極端に速い場合は、ダンゴが割れるまでにウキが海中に沈んでしまうという欠点もあります。
この場合はかなり浮力の大きい寝ウキを使う必要がありますので、小さいアタリは解りにくくなります。
お互いの欠点をカバーしつつ、浮力があり感度のよい寝ウキの最終形としては、とうがらし型の寝ウキということになります。
上の写真の寝ウキですが、根元の方が太く、先端に向かってだんだん細くなるようにテーパーを付けています。
これは普通の寝ウキに比べ、浮力があって感度が良い形状です。エサ取りの小さいアタリでも反応が良いです。
このタイプのウキはあまり市販されていないので、時間があれば自作してみてはいかがでしょう。
下の写真は直径8mmのバルサ材や桐材で作っています。11~17cmです。
市販で近いものと言えば、大西ウキというのもこのような形状をしていて人気があります。
下の写真の上3つが大西ウキです。
ウキの色は、私の経験では蛍光のオレンジが最も見やすく、次に蛍光の赤、蛍光の黄色、蛍光の緑となります。
ただし状況によっては順番が前後する場合もあります。
また、夕日が眩しい場合は黒いウキを使うと見やすくなりますので、ひとつ持っておくと便利でしょう。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。