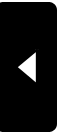チヌの数釣りのコツ
チヌの数釣りのコツ
夏から秋のシーズンは、小型の数釣りが楽しめます。
二桁釣果は当たり前で、人によっては20匹、30匹という大釣りも可能です。

しかし、そうは言ってもなかなか思うようにチヌが釣れない人も多いと思います。
数釣りのコツを書いてみようと思います。
ポイント設定
たくさんのチヌを釣るには、たくさんのチヌを集めることです。
まず最初に集める場所(ポイント)を決めます。
ポイント設定で大切なのは、一日の釣りのプランを考えることです。
分かりやすく言うと、風の向きや強さ、潮の流れなど、自然条件の変化を予測し、ポイントの設定をするということです。
たとえば今は潮が流れていなくても、午後になって右から左に流れるだろうと予想される場合は、釣り座より少し右側にポイントを設定しておきます。
通い慣れた釣り場なら、だいたい分かると思いますが、とにかく先を読んで釣りをすることが大切です。
チヌを集める
ポイントが決まったら、そこへ集中してダンゴを投げます。
最初のうちは魚が何もいない状態なので、自然にダンゴが割れる硬さにします。
タナは底トントンに設定し、ダンゴの割れやエサ取りなどを観察します。
エサ取りが寄ってくると、ダンゴの割れが少し早くなりますが、それに合わせてダンゴを硬く握り割れ具合を調整します。
通常、ダンゴが底についてから15秒から20秒ぐらいで割れるのがちょうどいいと思います。
ただし、ウキの浮力とも関連するので、とにかくウキがしっかり馴染んでから割れるというのが前提となります。
以降はダンゴの投入を繰り返しますが、アタリがあっても無くても、また、サシエが取られても取られなくても、ダンゴが割れたら5~10秒ぐらい流して仕掛けを回収するようにします。
エサ取りが増えてくると、ダンゴが割れた直後にサシエを取られる事が多くなるので、空バリの時間を無くすために回収の時間を決めるわけです。
よく仕掛けを潮下へ流してアタリを待つ人がいますが、ダラダラ流しても意味がありません。
そのうちサシエはダンゴが割れた瞬間に取られるようになりますので・・・。
ダンゴを底まで沈める
ダンゴの投入を繰り返すと、やがてエサ取りの猛攻が始まります。
このような変化は、紀州釣りの楽しみのひとつですが、徐々に対策が必要になってくるタイミングでもあります。
エサ取りが増えてくると、アタリもなくサシエを取られるのは当たり前で、ボラやアジの大群などが中層でダンゴにアタックし、ダンゴを割ってしまうこともあります。
ダンゴが底まで持たないと、チヌは釣れません。
この場合、どんな手段を使ってもよいので、とにかくダンゴを底に沈めることが第一です。
まず、ダンゴを硬くする。次にダンゴを大きくする。それでもダメなら水分を少し多めにします。
この時、あまり無茶苦茶に硬くすると着底してから全く割れませんので、その辺も考慮して硬さを決めます。
実は、ダンゴの硬さというのはチヌが寄ってからも非常に重要になるのですが、そのへんはまた後で記述します。
サシエでの対応は無駄?

エサ取りがあまりにも多いと、サシエを取られにくいものに変えて対処したくなります。
サシエを変えることによって、エサ取りにサシエを取られるまでの時間を少しでも稼ぐという意味では、それまで釣れなかったチヌが釣れることはあります。
しかし、サシエを変えても、根本的な解決にはなりません。
チヌの数釣りのコツは、チヌを集めることであって、エサ取りをかわす事ではないからです。
とにかくポイントにたくさんのチヌを集めて、エサ取りよりも強い勢力に変えていくことが何より重要です。
「チヌの群れが足を止めてダンゴを突ついて食う」
これをイメージします。
実際にこういう状況を作ることで、エサ取りよりも先にチヌが食って来るようになります。
ダンゴをもっと硬く・・・
チヌが食うまでの時間を稼ぐことは数釣りでは大切です。
サシエを変えることは根本的な解決策にはなりませんが、魚の目先を変えるなど、少しでも数を稼ぐなら有効な手段かもしれません。
しかしチヌが食うまでの時間を稼ぐ上で最も効果的な方法があります。
それは、紀州釣りの武器であるダンゴを硬くするということです。
紀州釣りだからこそ出来る方法であり、これこそが紀州釣りの真骨頂です。

ダンゴを硬くすることは、チヌが寄ってからも非常に重要だ、と前の項で書きましたが、もう少し詳しく書いてみます。
ダンゴの投入を繰り返し、チヌがたくさん寄ってきても、一方でどんどんチヌを釣り上げているとチヌの数が少し減ってきます。
また、チヌの群れの中には潮に乗ってポイントから移動してしまう集団も出てきます。
さらに濁りが拡散してチヌが少し散らばってしまうこともよくあります。
釣り人から見ると「食い渋り」という状況にも見えます。
こういう状態になると、またエサ取りの勢力が強くなって、サシエをすぐに取られ、チヌは釣れなくなります。
対処法として最も効果的なのは、ダンゴをさらに硬くすることです。
硬いダンゴにすると、エサ取りがいくら突ついてもなかなか割れません。
エサ取りがダンゴに群がる光景はチヌにとって魅力的なのかどうかわかりませんが、硬いダンゴで時間を稼いていると、そこに必ずチヌが割って入ってきます。
どんなに硬いダンゴでもチヌにかかれば一撃です。
チヌ自身がダンゴを割って、濁りを出して、ついでにサシエも食ってくれます。
もしすぐにチヌが食わなくても、これを3回ほど繰り返すと、濁りによってポイントが明確になり、少し散らばっていたチヌが集まるようになり、また釣れ出します。
ポイントのイメージと仕掛けの流し方
ダンゴが割れて、右へ流れるか左へ流れるかで、チヌが食ってきたり食ってこなかったりすることがよくあります。
特にダンゴを遠くに投げる人は、仕掛けを流す方向により釣果がまるで変わってきます。
ダンゴ投入後のウキの位置と道糸の位置を調整し、仕掛けを流す方向をうまくコントロールします。
もう少し分かりやすく説明します。
たとえば、チヌが集まっているポイントが2メートルの円内だとします。
その円内の左ギリギリにダンゴを投げた場合、右に流れるとチヌが釣れますが、左に流れるとポイントから外れチヌは釣れません。
奥に流れたり、手前に流れても同じことです。
海では風や潮の流れがあって、しかも場所によって微妙に違いがあります。
どこも同じような潮の流れだと思っていても、手前と奥では随分違ったりします。
ダンゴ投入後、これらのことを考慮し、ポイント円内へ仕掛けを誘導するようにします。
チヌが散らばっていてポイントがはっきり分からない場合は、自分の描いているポイントをイメージします。
あくまでも自分の描いているポイントですので、間違ってたら次に修正すればOKです。
風や潮流が強すぎて仕掛けのコントロールが不能と思える場合でも、道糸を張ったり緩めたりするだけで、仕掛けが流れる方向が変わることがあります。
状況の変化に伴うタナの調整
チヌの数釣りは、動作としては同じ事の繰り返しで、それをどれだけ正確に行えるかということが大切です。
しかし、一日釣りをしている中で、実は状況というのは刻一刻と変化しています。
その変化にどう対応するかによって、釣果は大きく変わってきます。
同じ事の繰り返しのようでも、釣り人はいろいろやってるわけです。
その分かりやすい例がタナ調整(ウキ下の調整)です。
今回の数釣りの説明では、釣り始めはトントンのタナでやっています。
では、ずっとトントンのタナで良いのかというと、それは違います。
風や潮流が強くなり、仕掛けが浮き上がるとチヌの食いに影響します。
かと言って、ハワセすぎるとアタリが分からないばかりか、いつダンゴが割れたかも分かりません。
大切なのは、チヌが食いやすく、アタリが分かりやすいこと。また、ウキの変化によって海底の魚の様子が分かることです。
海底の魚の様子というのは、ダンゴの割れ具合とか、エサ取りの状況などです。
実は釣り人にとって、ウキの動きだけしか海底の情報を得る手段はないのです。
タナ調整をきっちりやってると、今まで見えなかったものが見えてくるかもしれません。
夏から秋のシーズンは、小型の数釣りが楽しめます。
二桁釣果は当たり前で、人によっては20匹、30匹という大釣りも可能です。
しかし、そうは言ってもなかなか思うようにチヌが釣れない人も多いと思います。
数釣りのコツを書いてみようと思います。
ポイント設定
たくさんのチヌを釣るには、たくさんのチヌを集めることです。
まず最初に集める場所(ポイント)を決めます。
ポイント設定で大切なのは、一日の釣りのプランを考えることです。
分かりやすく言うと、風の向きや強さ、潮の流れなど、自然条件の変化を予測し、ポイントの設定をするということです。
たとえば今は潮が流れていなくても、午後になって右から左に流れるだろうと予想される場合は、釣り座より少し右側にポイントを設定しておきます。
通い慣れた釣り場なら、だいたい分かると思いますが、とにかく先を読んで釣りをすることが大切です。
チヌを集める
ポイントが決まったら、そこへ集中してダンゴを投げます。
最初のうちは魚が何もいない状態なので、自然にダンゴが割れる硬さにします。
タナは底トントンに設定し、ダンゴの割れやエサ取りなどを観察します。
エサ取りが寄ってくると、ダンゴの割れが少し早くなりますが、それに合わせてダンゴを硬く握り割れ具合を調整します。
通常、ダンゴが底についてから15秒から20秒ぐらいで割れるのがちょうどいいと思います。
ただし、ウキの浮力とも関連するので、とにかくウキがしっかり馴染んでから割れるというのが前提となります。
以降はダンゴの投入を繰り返しますが、アタリがあっても無くても、また、サシエが取られても取られなくても、ダンゴが割れたら5~10秒ぐらい流して仕掛けを回収するようにします。
エサ取りが増えてくると、ダンゴが割れた直後にサシエを取られる事が多くなるので、空バリの時間を無くすために回収の時間を決めるわけです。
よく仕掛けを潮下へ流してアタリを待つ人がいますが、ダラダラ流しても意味がありません。
そのうちサシエはダンゴが割れた瞬間に取られるようになりますので・・・。
ダンゴを底まで沈める
ダンゴの投入を繰り返すと、やがてエサ取りの猛攻が始まります。
このような変化は、紀州釣りの楽しみのひとつですが、徐々に対策が必要になってくるタイミングでもあります。
エサ取りが増えてくると、アタリもなくサシエを取られるのは当たり前で、ボラやアジの大群などが中層でダンゴにアタックし、ダンゴを割ってしまうこともあります。
ダンゴが底まで持たないと、チヌは釣れません。
この場合、どんな手段を使ってもよいので、とにかくダンゴを底に沈めることが第一です。
まず、ダンゴを硬くする。次にダンゴを大きくする。それでもダメなら水分を少し多めにします。
この時、あまり無茶苦茶に硬くすると着底してから全く割れませんので、その辺も考慮して硬さを決めます。
実は、ダンゴの硬さというのはチヌが寄ってからも非常に重要になるのですが、そのへんはまた後で記述します。
サシエでの対応は無駄?
エサ取りがあまりにも多いと、サシエを取られにくいものに変えて対処したくなります。
サシエを変えることによって、エサ取りにサシエを取られるまでの時間を少しでも稼ぐという意味では、それまで釣れなかったチヌが釣れることはあります。
しかし、サシエを変えても、根本的な解決にはなりません。
チヌの数釣りのコツは、チヌを集めることであって、エサ取りをかわす事ではないからです。
とにかくポイントにたくさんのチヌを集めて、エサ取りよりも強い勢力に変えていくことが何より重要です。
「チヌの群れが足を止めてダンゴを突ついて食う」
これをイメージします。
実際にこういう状況を作ることで、エサ取りよりも先にチヌが食って来るようになります。
ダンゴをもっと硬く・・・
チヌが食うまでの時間を稼ぐことは数釣りでは大切です。
サシエを変えることは根本的な解決策にはなりませんが、魚の目先を変えるなど、少しでも数を稼ぐなら有効な手段かもしれません。
しかしチヌが食うまでの時間を稼ぐ上で最も効果的な方法があります。
それは、紀州釣りの武器であるダンゴを硬くするということです。
紀州釣りだからこそ出来る方法であり、これこそが紀州釣りの真骨頂です。

ダンゴを硬くすることは、チヌが寄ってからも非常に重要だ、と前の項で書きましたが、もう少し詳しく書いてみます。
ダンゴの投入を繰り返し、チヌがたくさん寄ってきても、一方でどんどんチヌを釣り上げているとチヌの数が少し減ってきます。
また、チヌの群れの中には潮に乗ってポイントから移動してしまう集団も出てきます。
さらに濁りが拡散してチヌが少し散らばってしまうこともよくあります。
釣り人から見ると「食い渋り」という状況にも見えます。
こういう状態になると、またエサ取りの勢力が強くなって、サシエをすぐに取られ、チヌは釣れなくなります。
対処法として最も効果的なのは、ダンゴをさらに硬くすることです。
硬いダンゴにすると、エサ取りがいくら突ついてもなかなか割れません。
エサ取りがダンゴに群がる光景はチヌにとって魅力的なのかどうかわかりませんが、硬いダンゴで時間を稼いていると、そこに必ずチヌが割って入ってきます。
どんなに硬いダンゴでもチヌにかかれば一撃です。
チヌ自身がダンゴを割って、濁りを出して、ついでにサシエも食ってくれます。
もしすぐにチヌが食わなくても、これを3回ほど繰り返すと、濁りによってポイントが明確になり、少し散らばっていたチヌが集まるようになり、また釣れ出します。
ポイントのイメージと仕掛けの流し方
ダンゴが割れて、右へ流れるか左へ流れるかで、チヌが食ってきたり食ってこなかったりすることがよくあります。
特にダンゴを遠くに投げる人は、仕掛けを流す方向により釣果がまるで変わってきます。
ダンゴ投入後のウキの位置と道糸の位置を調整し、仕掛けを流す方向をうまくコントロールします。
もう少し分かりやすく説明します。
たとえば、チヌが集まっているポイントが2メートルの円内だとします。
その円内の左ギリギリにダンゴを投げた場合、右に流れるとチヌが釣れますが、左に流れるとポイントから外れチヌは釣れません。
奥に流れたり、手前に流れても同じことです。
海では風や潮の流れがあって、しかも場所によって微妙に違いがあります。
どこも同じような潮の流れだと思っていても、手前と奥では随分違ったりします。
ダンゴ投入後、これらのことを考慮し、ポイント円内へ仕掛けを誘導するようにします。
チヌが散らばっていてポイントがはっきり分からない場合は、自分の描いているポイントをイメージします。
あくまでも自分の描いているポイントですので、間違ってたら次に修正すればOKです。
風や潮流が強すぎて仕掛けのコントロールが不能と思える場合でも、道糸を張ったり緩めたりするだけで、仕掛けが流れる方向が変わることがあります。
状況の変化に伴うタナの調整
チヌの数釣りは、動作としては同じ事の繰り返しで、それをどれだけ正確に行えるかということが大切です。
しかし、一日釣りをしている中で、実は状況というのは刻一刻と変化しています。
その変化にどう対応するかによって、釣果は大きく変わってきます。
同じ事の繰り返しのようでも、釣り人はいろいろやってるわけです。
その分かりやすい例がタナ調整(ウキ下の調整)です。
今回の数釣りの説明では、釣り始めはトントンのタナでやっています。
では、ずっとトントンのタナで良いのかというと、それは違います。
風や潮流が強くなり、仕掛けが浮き上がるとチヌの食いに影響します。
かと言って、ハワセすぎるとアタリが分からないばかりか、いつダンゴが割れたかも分かりません。
大切なのは、チヌが食いやすく、アタリが分かりやすいこと。また、ウキの変化によって海底の魚の様子が分かることです。
海底の魚の様子というのは、ダンゴの割れ具合とか、エサ取りの状況などです。
実は釣り人にとって、ウキの動きだけしか海底の情報を得る手段はないのです。
タナ調整をきっちりやってると、今まで見えなかったものが見えてくるかもしれません。
この記事へのコメント
お久しぶりです。
以前、仕掛けについてご教授頂きましてありがとうございました。
今日、数釣りにチャレンジしてみようと思って、ここのページを参照いたしました。
今までは潮があってもダンゴが割れてから2分位たってから回収というようなやりかたしてまして・・・。
今日はダンゴが割れてから30秒で回収を心がけてしてましたら、チヌの群れ?に遭遇して(タナはもちろんトントン)4時間でチヌ7・ヘダイ1・コロダイ1で、大きさはほぼ35cm以上ありました。二桁を目標でしたがw
でも、9匹なんて驚きと紀州釣りにこだわってやってきた事が嬉しいです!!
このブログを何回も読み直したりして実践することで良い感じになってきてます。
ありがとうございます。
一つ質問なんですが、ウキの浮力が2Bから5Bまでの玉ウキを使っています。いつもは3Bがメインで今日は5Bを使ったところ団子の割れた時がわかりやすかったのですが、チヌのあたりでウキの沈む距離が短かったです。3Bの場合だと潮でダンゴしもりで当たってるのが確信がもてなかったり、釣れる時のあたりはウキが完全に消しこんでからだったりで、2~4枚が限度でした。フカセ釣りでは極力ウキの浮力をなくす方が良いとされていますが、紀州釣りではウキの浮力は深さとかあたりの取り方とかでどのようにすればいいかなっと疑問でした。
時間があるときでよろしいのでお願いします。
以前、仕掛けについてご教授頂きましてありがとうございました。
今日、数釣りにチャレンジしてみようと思って、ここのページを参照いたしました。
今までは潮があってもダンゴが割れてから2分位たってから回収というようなやりかたしてまして・・・。
今日はダンゴが割れてから30秒で回収を心がけてしてましたら、チヌの群れ?に遭遇して(タナはもちろんトントン)4時間でチヌ7・ヘダイ1・コロダイ1で、大きさはほぼ35cm以上ありました。二桁を目標でしたがw
でも、9匹なんて驚きと紀州釣りにこだわってやってきた事が嬉しいです!!
このブログを何回も読み直したりして実践することで良い感じになってきてます。
ありがとうございます。
一つ質問なんですが、ウキの浮力が2Bから5Bまでの玉ウキを使っています。いつもは3Bがメインで今日は5Bを使ったところ団子の割れた時がわかりやすかったのですが、チヌのあたりでウキの沈む距離が短かったです。3Bの場合だと潮でダンゴしもりで当たってるのが確信がもてなかったり、釣れる時のあたりはウキが完全に消しこんでからだったりで、2~4枚が限度でした。フカセ釣りでは極力ウキの浮力をなくす方が良いとされていますが、紀州釣りではウキの浮力は深さとかあたりの取り方とかでどのようにすればいいかなっと疑問でした。
時間があるときでよろしいのでお願いします。
アサさん、こんにちは。
紀州釣りで、チヌの数釣りが楽しめるようになってきたのですね!
>チヌの群れ?に遭遇して
チヌの数釣りの極意は、ダンゴ投入のテンポを速くして、1匹でも多く活性の高いチヌを集めることです。
今度はぜひ二桁を期待しています。
>5Bを使ったところチヌのあたりでウキの沈む距離が短かったです
浮力が大きければ確かにウキが沈みにくいことはあります。
ただ、ウキを少し押さえ込む程度のアタリは、タナやチヌの活性の関係でよくあることです。小さなアタリでもそのウキ独特のチヌアタリを楽しめれば良いと思います。
ウキの沈む距離というのはウキの浮力だけでなく、道糸がフロートの場合とサスペンドの場合でも違ってきますし、サルカンの大きさや潮の流れなどの要素も絡み合ってきますので一概には言えません。
>フカセ釣りでは極力ウキの浮力をなくす方が良いとされていますが
紀州釣りの場合は、ダンゴの重さに対し、ある程度踏ん張りが効く浮力のあるウキが必要です。
チヌの食いを良くするためには、ウキの浮力を小さくするのではなく仕掛けをハワセます。
ただし、チヌの数釣りの場合は、食い気のないチヌを追いかけまわして無駄に時間を浪費するのではなく、やる気のない魚はとりあえずほっといて、ダンゴの打ち返しでチヌの活性を上げて食い気のあるチヌだけを狙って数を釣るのがコツです。
ところでウキの浮力に関してですが、ウキの浮力を決める要因は、次の4つです。
1つ目は水深、2つ目は潮流、3つ目はハワセ幅、4つ目は遠投です。
これらの条件を考慮して最もバランスの良いウキを選ぶようにします。
ダンゴの割れが確認でき、さらにチヌのアタリが明確に分かるウキです。
水深のあるところでは浮力の大きいウキを使います。
潮流の速い時も浮力の大きいウキを使います。
ハワセ幅の小さいトントンの時も浮力の大きいウキを使います。
遠投するときも浮力の大きいウキを使います。
道糸が風や潮流ではらみますので、その分ウキに負担が掛かるからです。
足元やチョイ投げ程度ならウキの浮力は小さくても問題ありません。
浮力の大きいウキの利点は、タナを合わせやすいのと、大きく明確なアタリが出ることです。ただし、タナが合っていないと、ほとんどアタリが出ないことがあります。
タナ合わせが苦手な人は、浮力の小さいウキを使って大きめにハワセるのも1つの方法です。
浮力の小さいウキの利点ですが、紀州釣りでも中層でグレを狙う場合なら小さいウキの方が食い込みも良くアタリも大きく出ます。
フカセ釣りでも同じだと思いますが、浮力の小さいウキの方が仕掛けが潮に馴染みやすくて食いが良いということもあります。
紀州釣りでチヌを狙う時は海底を狙いますので、浮力の小さすぎるウキはアタリがぼやけて本命の小さなアタリが余計に分かりづらくなります。
紀州釣りの場合はウキの浮力よりも、ダンゴやタナ、流し方、サシエサなどが圧倒的にチヌの食いに影響します。
もし、チヌの活性が低く、食いが悪いと思った時は、ウキや仕掛けを変えるよりも、大きめにハワセてできるだけ違和感なく食わせるようにします。
>紀州釣りではウキの浮力は深さとかあたりの取り方とかでどのように・・・
水深とウキの浮力の関係ですが、私はだいたい水深3~4ヒロくらいなら1号程度の寝ウキを使います。
釣具店で売っている寝ウキもだいたいそんなもんです。
最近私がよく行く釣場は水深8ヒロですが、潮が緩いので寝ウキの浮力は1.5号程度です。
浮力が結構ありますが、寝ウキですのでチヌアタリやエサ取りの微妙なアタリも明確に出ます。
ただし、タナが合っていない時は小さなアタリは出ず、いきなりウキが消し込むこともあります。
ダンゴを遠投せず、足元を狙う時は同じ水深でも5B程度の寝ウキを使います。
アタリの取り方というのは、どんなウキを使っていても基本は同じだと思います。
ウキによってアタリの出方が違いますが、その中のチヌアタリだけを見極めて取っていくということです。
ウキが震える程度の極小アタリでも、チヌが食っていると確信できれば思いっきりアワセます。
チヌの食い込みが悪いと思えば、ウキが完全に消し込むまで合わせません。
アタリの大小や、ウキが沈む、沈まないはその時のチヌの活性や潮の動きなどで変わってきますのであまり気にすることはありません。
アタリの取り方によって浮力を変えるのではなく、使うウキの浮力に合ったタナに設定し、アワセのタイミングもそれに合わせることです。
チヌのアタリは本当に千差万別ですので、いろんなパターンのチヌアタリを楽しめば良いと思いますよ。
紀州釣りで、チヌの数釣りが楽しめるようになってきたのですね!
>チヌの群れ?に遭遇して
チヌの数釣りの極意は、ダンゴ投入のテンポを速くして、1匹でも多く活性の高いチヌを集めることです。
今度はぜひ二桁を期待しています。
>5Bを使ったところチヌのあたりでウキの沈む距離が短かったです
浮力が大きければ確かにウキが沈みにくいことはあります。
ただ、ウキを少し押さえ込む程度のアタリは、タナやチヌの活性の関係でよくあることです。小さなアタリでもそのウキ独特のチヌアタリを楽しめれば良いと思います。
ウキの沈む距離というのはウキの浮力だけでなく、道糸がフロートの場合とサスペンドの場合でも違ってきますし、サルカンの大きさや潮の流れなどの要素も絡み合ってきますので一概には言えません。
>フカセ釣りでは極力ウキの浮力をなくす方が良いとされていますが
紀州釣りの場合は、ダンゴの重さに対し、ある程度踏ん張りが効く浮力のあるウキが必要です。
チヌの食いを良くするためには、ウキの浮力を小さくするのではなく仕掛けをハワセます。
ただし、チヌの数釣りの場合は、食い気のないチヌを追いかけまわして無駄に時間を浪費するのではなく、やる気のない魚はとりあえずほっといて、ダンゴの打ち返しでチヌの活性を上げて食い気のあるチヌだけを狙って数を釣るのがコツです。
ところでウキの浮力に関してですが、ウキの浮力を決める要因は、次の4つです。
1つ目は水深、2つ目は潮流、3つ目はハワセ幅、4つ目は遠投です。
これらの条件を考慮して最もバランスの良いウキを選ぶようにします。
ダンゴの割れが確認でき、さらにチヌのアタリが明確に分かるウキです。
水深のあるところでは浮力の大きいウキを使います。
潮流の速い時も浮力の大きいウキを使います。
ハワセ幅の小さいトントンの時も浮力の大きいウキを使います。
遠投するときも浮力の大きいウキを使います。
道糸が風や潮流ではらみますので、その分ウキに負担が掛かるからです。
足元やチョイ投げ程度ならウキの浮力は小さくても問題ありません。
浮力の大きいウキの利点は、タナを合わせやすいのと、大きく明確なアタリが出ることです。ただし、タナが合っていないと、ほとんどアタリが出ないことがあります。
タナ合わせが苦手な人は、浮力の小さいウキを使って大きめにハワセるのも1つの方法です。
浮力の小さいウキの利点ですが、紀州釣りでも中層でグレを狙う場合なら小さいウキの方が食い込みも良くアタリも大きく出ます。
フカセ釣りでも同じだと思いますが、浮力の小さいウキの方が仕掛けが潮に馴染みやすくて食いが良いということもあります。
紀州釣りでチヌを狙う時は海底を狙いますので、浮力の小さすぎるウキはアタリがぼやけて本命の小さなアタリが余計に分かりづらくなります。
紀州釣りの場合はウキの浮力よりも、ダンゴやタナ、流し方、サシエサなどが圧倒的にチヌの食いに影響します。
もし、チヌの活性が低く、食いが悪いと思った時は、ウキや仕掛けを変えるよりも、大きめにハワセてできるだけ違和感なく食わせるようにします。
>紀州釣りではウキの浮力は深さとかあたりの取り方とかでどのように・・・
水深とウキの浮力の関係ですが、私はだいたい水深3~4ヒロくらいなら1号程度の寝ウキを使います。
釣具店で売っている寝ウキもだいたいそんなもんです。
最近私がよく行く釣場は水深8ヒロですが、潮が緩いので寝ウキの浮力は1.5号程度です。
浮力が結構ありますが、寝ウキですのでチヌアタリやエサ取りの微妙なアタリも明確に出ます。
ただし、タナが合っていない時は小さなアタリは出ず、いきなりウキが消し込むこともあります。
ダンゴを遠投せず、足元を狙う時は同じ水深でも5B程度の寝ウキを使います。
アタリの取り方というのは、どんなウキを使っていても基本は同じだと思います。
ウキによってアタリの出方が違いますが、その中のチヌアタリだけを見極めて取っていくということです。
ウキが震える程度の極小アタリでも、チヌが食っていると確信できれば思いっきりアワセます。
チヌの食い込みが悪いと思えば、ウキが完全に消し込むまで合わせません。
アタリの大小や、ウキが沈む、沈まないはその時のチヌの活性や潮の動きなどで変わってきますのであまり気にすることはありません。
アタリの取り方によって浮力を変えるのではなく、使うウキの浮力に合ったタナに設定し、アワセのタイミングもそれに合わせることです。
チヌのアタリは本当に千差万別ですので、いろんなパターンのチヌアタリを楽しめば良いと思いますよ。
いつもご丁寧にありがとうございます。
地元では紀州釣りの方は殆んどいなくて、釣具やさんにも寝ウキは置いてないですw
でも、いまあるウキ類で色々と試行錯誤しながら楽しんでいきたいと思います。
チヌの本当たりが見極められるようがんばります。
地元では紀州釣りの方は殆んどいなくて、釣具やさんにも寝ウキは置いてないですw
でも、いまあるウキ類で色々と試行錯誤しながら楽しんでいきたいと思います。
チヌの本当たりが見極められるようがんばります。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。